自然災害や火災により家屋や物品が被害を受けた場合、その被害を証明するための書類として罹災証明書と被災証明書が発行されます。
これらの証明書は、保険金の請求、被災者支援制度の利用、税金の減免などを受ける際に必要となる重要な書類です。
それぞれの違いや申請方法、手続きの流れについて詳しく解説します。
罹災証明書と被災証明書とは

罹災証明書と被災証明書について詳しく説明していきたいと思います。
罹災証明書(りさいしょうめいしょ)
罹災証明書は、火災や自然災害による住宅の被害状況を自治體(じちたい)が調査し、その結果を証明するための書類です。家屋が「全壊」「半壊」「一部損壊」など、どの程度の被害を受けているかを示すもので、以下のような目的で使用されます。
- 使用目的
- 被災者生活再建支援金の申請
- 各種税金の減免
- 災害見舞金、見舞品の受給
- 住宅の再建・補修費用の融資申請
- 共済金・火災保険などの支払い請求
生命保険や損害保険の保険金請求においては、必ずしも必要ではない場合もありますが、税金の減免や支援金の申請にはほとんどの場合、必要となります。
被災証明書
一方、「被災証明書」は住宅以外のもの、例えば店舗、工場、車、家財、屋外の設置物などが災害により被害を受けたことを証明するための書類です。こちらは、住宅ではなく資産全般に対する被害を示すもので、以下のようなケースで必要となります。
- 使用目的
- 自動車の保険請求
- 商業施設や工場の被災時の保険金請求
- 各種被災者支援制度の利用
罹災証明書と被災証明書の違い
以下に罹災証明書と被災証明書の違いを表にまとめました。
| 項目 | 罹災証明書 | 被災証明書 |
|---|---|---|
| 対象 | 住宅 | 住宅以外(店舗、車、家財など) |
| 調査 | 市区町村による現地調査あり | 調査なし(写真等による確認) |
| 利用目的 | 住宅再建支援、税金の減免、融資申請 | 保険請求、家財・設備の被害証明 |
罹災証明書と被災証明書のメリットとは?
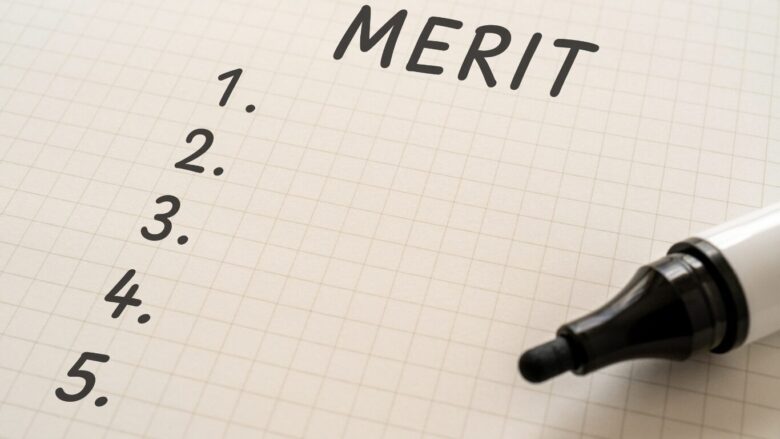
自然災害や火災による被害を証明するための書類として「罹災証明書」と「被災証明書」があります。それぞれのメリットついて詳しく解説します。
罹災証明書のメリット
罹災証明書は、火災や自然災害によって住宅が被害を受けた際、その被害の程度を証明するための書類です。被災者支援金の申請や税金の減免、融資の申請など、災害後の生活再建に不可欠な書類となります。
- 公的支援や補助金の申請に必要
被災者生活再建支援金の申請や各種補助金の受給に必須となるため、迅速な生活再建が可能です。 - 税金の減免
被災により住宅が損害を受けた場合、所得税や固定資産税などの減免措置を受けられます。 - 住宅ローンや融資の申請がスムーズ
被災による住宅再建や修繕のためのローン申請に利用できます。 - 災害見舞金や見舞品の受け取り
罹災証明書を提示することで、自治體(じちたい)や保険会社から見舞金や物資を受け取ることが可能です。
被災証明書のメリット
被災証明書は、店舗や工場、車、家財、屋外の設置物など、住宅以外の被害を証明するための書類です。自然災害による住宅以外の被害を証明する場合に活用されます。
- 自動車や店舗の保険請求に利用
自動車の損害保険や店舗、工場の火災保険などの保険金請求に必要です。 - 被災者支援制度の利用が可能
店舗や工場が被害を受けた場合でも、被災証明書を用いることで支援制度の利用ができます。 - 多様な被害をカバー
家屋だけでなく、自動車や設備、家財などの被害も証明できるため、幅広い損害に対処できます。 - 家財の補償
家財に対する損害の証明として、保険金の請求や被災者支援制度の利用に役立ちます。
罹災証明書・被災証明書の申請の流れ

罹災証明書・被災証明書の申請の流れについてご説明します。
罹災証明書の申請手順
- 被害状況の確認
- 申請前に、家屋の被害状況を撮影して記録しておくことが重要です。特に、損傷部分が明確にわかるように、外観は4方向から、内部も可能な限り詳細に撮影します。
- 水害の場合は、浸水の深さが分かるように写真を撮影します。
- 必要書類の準備
- 申請書(市区町村によって書式が異なります)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被害箇所の写真(被害状況を明確に示すもの)
- 建物の図面や契約書などの補足資料(必要な場合)
- 申請方法
- お住まいの市区町村の役所や、災害の場合は所轄の消防署に申請します。
- 市区町村によっては、郵送や電子申請が可能な場合もあります。
- 現地調査
- 申請後、自治體(じちたい)の職員が現地調査を行い、被害の程度を確認します。自己判定方式を選択した場合は、写真のみでの確認となり、現地調査は行われません。
- 証明書の交付
- 調査結果に基づき、証明書が交付されます。交付までの期間は自治體(じちたい)によって異なりますが、数週間から1か月程度かかる場合があります。
被災証明書の申請手順
- 被害状況の確認
- 住宅以外の被害状況を記録します。自動車の場合は、車體(しゃたい)の損傷部分を様々な角度から撮影します。商業施設や工場の場合も、建物全體(ぜんたい)や設備の被害箇所を詳細に記録します。
- 必要書類の準備被災マンション法の適用を受けるためには、区分所有者または敷地共有者による集会を開き、決議を行う必要があります。しかし、災害直後は連絡が取りづらい状況が続くことが多いため、通常の集会と比べて特別な招集・通知方法が認められています。
- 集会招集の流れ
- 招集権者の決定
- 既存の管理者がいれば、その者が招集する。
- 管理者が不在の場合は、区分所有者または敷地共有者の5分の1以上の議決権を持つ者が招集できる。
- 通知の方法
- 通常のケースでは、集会の日の2か月前までに、全員に通知を送る必要がある。
- ただし、災害時は郵便や電話が機能しない可能性があるため、マンションの敷地内の見やすい場所への掲示が認められる。
- 掲示を行った場合、別途できる限りの方法で連絡を試みることが求められる。
- 集会の開催
- 指定された日時に集会を開き、再建や売却についての決議を行う。
- 5分の4以上の賛成を得ることで、再建や売却が決定する。
- 通知を適切に行わないと、決議が無効となる可能性もあるため、事前に手順をしっかり確認しておくことが重要です。
- 申請書(市区町村によって書式が異なります)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 被害状況の写真
- 申請方法
- お住まいの市区町村役所に提出します。郵送や電子申請が可能な場合もあります。
- 証明書の交付
- 被害状況の確認後、証明書が交付されます。
申請の際の注意点
- 自己判定方式について
自己判定方式を利用する場合、被害箇所を撮影した写真を提出することで現地調査に代えられます。ただし、この方式は「一部損壊」に該当する場合のみ利用可能です。 - 証明書の交付期間
災害発生直後は申請が集中し、交付までに時間がかかることがあります。早めの申請を心がけましょう。 - 申請先の確認
火災による被害の場合は消防署、自然災害の場合は市区町村役所が窓口となります。事前に確認しておくとスムーズです。
罹災証明書・被災証明書は何に使う?
- 税金の減免
被災により住宅や財産が損壊した場合、一定の条件下で固定資産税や所得税が減免される制度があります。申請には証明書の提示が必要です。 - 融資の申請
被災者生活再建支援金や被災者向けの融資を受ける際には、被害の程度を証明するために罹災証明書・被災証明書が求められます。 - 保険金請求
火災保険や自動車保険、その他損害保険を請求する際、被害の証明として必要となる場合があります。
電子申請の利用
政府が提供するマイナポータルを利用すれば、罹災証明書・被災証明書の申請をオンラインで行うことも可能です。オンライン申請を利用すると、書類の提出がスムーズで、窓口での手続きを避けることができます。
以下の記事では、被災マンション法の適用条件や、再建・売却の具体的な手続きについて詳しく解説しています。災害後のマンション再建をスムーズに進めるためのポイントを知ることで、適切な判断ができるようになります。
以下の記事では、被災者生活再建支援制度の対象条件や申請方法、支援金の詳細について解説しています。支援を受けるための手続きを理解することで、生活の再建に向けた準備を進めることができます。
まとめ
- 罹災証明書は住宅の被害を証明するもの
- 被災証明書は住宅以外の被害を証明するもの
- 申請には被害状況の写真や必要書類の準備が不可欠
- 市区町村役所や消防署で手続き可能で、電子申請も利用できます
被災時に必要な手続きを理解しておくことで、迅速に支援制度を活用できます。災害時の負担を軽減するためにも、事前に申請方法を確認し、必要な対策を準備しておくことが大切です。
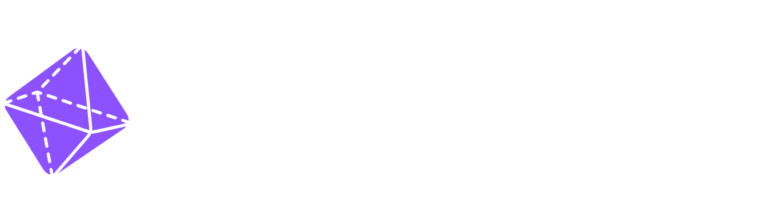
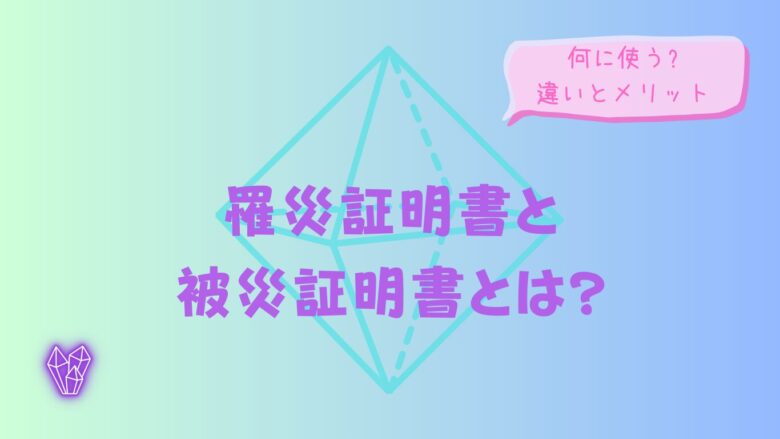

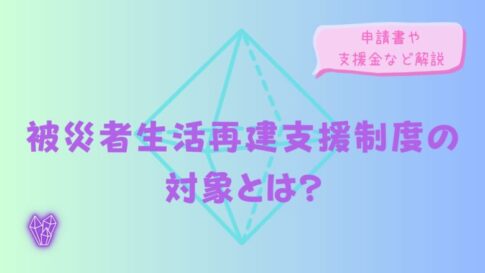
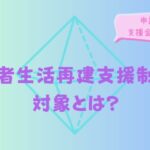



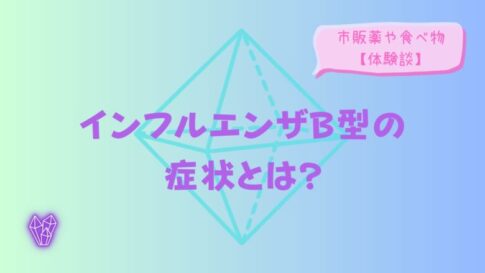
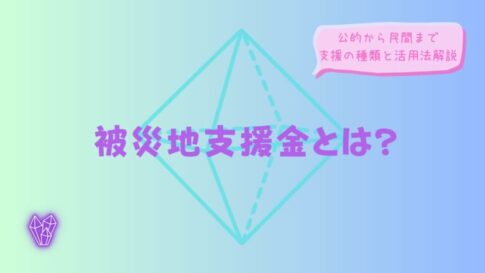
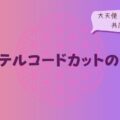
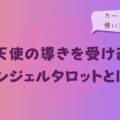
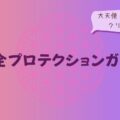
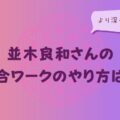
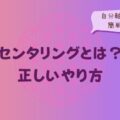
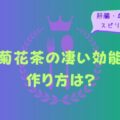
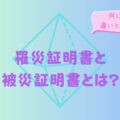
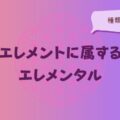
コメントを残す