インフルエンザB型って、A型とどう違うの?
熱が出ないこともあるって本当?
この記事では、症状の特徴や市販薬の選び方、食べやすい食事などについて、わかりやすく解説します。
體調(たいちょう)が氣になる方や看病中の方にも役立つ内容です。
もくじ
インフルエンザB型とは?症状など体験談

インフルエンザにはA型・B型・C型などがありますが、毎年のように流行するのはA型とB型です。
特に注目されやすいのは大規模な流行を引き起こすA型ですが、B型も1月〜3月ごろにかけて周期的に流行する傾向があり、見過ごすことはできません。
わたし自身、2024年3月にインフルエンザB型に感染しました。
息子からうつったのですが、最初は倦怠感と寒氣、強い頭痛から始まり、後に胃腸の不調が強く出て、長期間にわたって體調(たいちょう)が優れない日が続きました。
熱は思ったほど上がらず、微熱が続いたものの體(からだ)のだるさが強く、発症か3三日目ごろに食欲が無くなっていき、5日目からは水分しか摂れないほどの食欲不振と酷い下痢が続きました。
食事ができるようになったのは8日目頃、完全に食欲が戻ったのは11日目でした。
慢性的に頭痛を感じ、息子のお世話ができないくらいしんどかったです。
11日目になっても、精神的に何をしても楽しくない、考えが暗い状態が続き、軽快に動けるようになるまで、実に2週間かかりました。
インフルエンザB型とA型との違い
インフルエンザA型は、「ヘマグルチニン(H)」と「ノイラミニダーゼ(N)」という2つの抗原の組み合わせにより多くの亜型が存在し、変異のスピードも速いため、世界的な流行を引き起こしやすいのが特徴です。
一方、B型は「ビクトリア系統」と「山形系統」という2系統に分かれ、変異もゆるやかであるため、大流行にはなりにくいとされています。
A型とB型は症状の出方に違いがあることが知られています。
A型は突然の高熱と強い全身症状が特徴で、発熱・咳・喉の痛みが急激に始まります。
一方、B型は比較的発熱が穏やかで、消化器症状(下痢や腹痛)や微熱が続くケースが多く、症状の進行もややゆるやかな傾向があります。
ただし、B型にも厄介な一面があります。特に小児では高熱、嘔吐、下痢などの消化器症状が強く出やすく、重症化するリスクもあります。
インフルエンザB型の感染経路と予防ワクチンの種類
インフルエンザB型は、A型と同様に主に「飛沫感染」や「接触感染」によって広がります。
咳やくしゃみを通してウイルスが空氣中に飛散したり、手指を介して粘膜にウイルスが触れたりすることで感染します。
わたしの場合、はっきりとした感染経路は分かりませんが、息子が先に発症しており、家庭内での感染でした。
発症の直前、お台場へおもちゃを買いに出かけたこともあり、人混みによる接触の可能性も否定できません。
なお、インフルエンザのワクチンにはA型・B型両方に対応した「4価ワクチン」があり、予防に有効だそうです。
わたしは今回ワクチンを接種していなかったため、感染してしまいましたが、接種していれば症状が軽く済んだ可能性もあるのか。。。
考えてもわからないのですが、事実としてワクチン未接種のわたしは重症、看病してくれた叔母はワクチン接種済でうつりませんでした。
でも、叔母は旦那さんの血縁の方で、何しろ旦那さんご一家は體(からだ)がお強いのです。。。なので、ワクチンを打っていたからかからなかった、と断定はできません。
今までの人生経験から、體(からだ)が弱いと思うわたしはワクチンに負けそうに感じているので、この先もワクチン接種は検討していません。
小児に多い症状と合併症リスク
小児では、B型インフルエンザにおいて以下のような特徴が報告されています。
- 嘔吐や下痢などの消化器症状が強く出る
- 39℃を超える高熱になることがある
- けいれんや異常行動を伴うインフルエンザ脳症のリスクがある
- 基礎疾患があると重症化しやすい
我が家の息子もインフルエンザB型に感染しましたが、下垂体不全をもともと患っているため、低血糖も重なって入院が必要な状態となりました(6日間)。
特に小児では、普段よりも強い症状が出ることがあるため、早めの医療機関受診が重要です。
今回の入院でほんとうに助かったのは、生活クラブの保険です。簡単な資料提出で1か月も待たずご入金いただきました。
入院につきイロイロと出費があったので、とても心強かったです。
病院側の事情で個室に入れて戴いていましたが、もし部屋が空いても、このまま個室で、とすんなりお願いできたのも、保険があったからでした。
成人に多い症状と入院時の傾向
成人の場合、B型の症状はA型に比べて見過ごされがちです。高熱が出ないため軽症と思い込んでしまうこともありますが、以下のような症状が長引く傾向にあります。
- 微熱が長期間続く
- 胃腸症状(下痢・食欲不振)
- 慢性的な頭痛や倦怠感
- 氣分の落ち込み(メンタルへの影響)
わたし自身も、頭痛や微熱が続き、何よりも「空腹は感じるのに食べられない」という状態がつらく、夜間の症状も強くて睡眠がまともにとれない日が続きました。
発症から14日目までは體力(たいりょく)は完全には戻らず、氣分が滅入るような日がありました。
インフルエンザB型の潜伏期間と感染期間
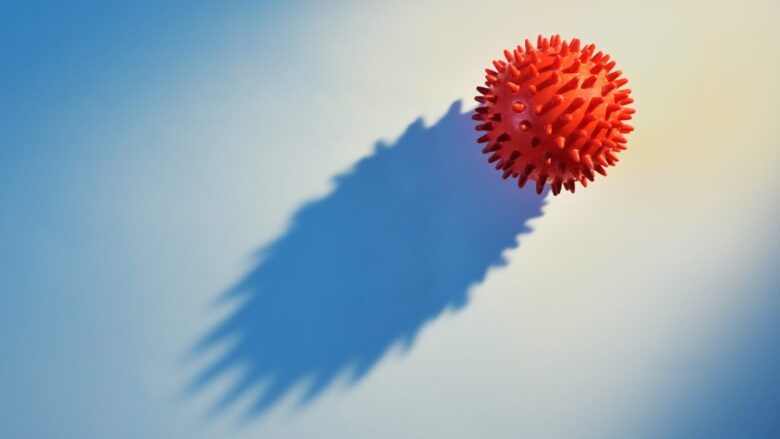
インフルエンザB型に感染した場合、症状が出るまでには一定の「潜伏期間」があります。
また、症状が出た後も他人へ感染させる「感染力のある期間」が存在します。
これらを理解しておくことで、周囲への感染拡大を防ぐ行動につながります。
潜伏期間の平均と発症のタイミング
インフルエンザB型の潜伏期間は、通常1〜4日、平均すると2日程度とされています。
ウイルスに感染してから體(からだ)の中で増殖し、症状が現れるまでに少し時間がかかるのが特徴です。
わたしの場合も、3月7日に息子が発症し、その翌日である8日にわたし自身が発症しました。ちょうど1日〜1.5日ほどの潜伏期間だったと思われます。
體のだるさや頭痛、悪寒といった症状が最初に現れたものの、発熱はさほど高くなく、氣づきにくい印象でした。
また、B型は症状がゆっくり始まることもあるため、「風邪かな?」と勘違いしやすく、潜伏期間後の初期対応が遅れがちになることもあります。
ワクチンの有効な期間が、発症から48時間以内だそうで(医師談)、B型の場合、難しく感じます。
発症から感染力がある期間について
インフルエンザのウイルスは、発症の1日前から他人に感染させる力を持っており、発症後5〜7日間ほどは感染力が続くとされています。
特に発症から2〜3日目がもっとも感染力が高く、周囲への配慮が必要な期間です。
症状が治まった後でも、免疫が回復しきっていない状態では再感染や別のウイルスへの感染リスクも高まるため、解熱後も数日は無理をせず、安静に過ごすことが大切です。
インフルエンザB型の診断方法と検査

インフルエンザB型かどうかを正確に判断するためには、医療機関での検査が欠かせません。
とくに初期症状が風邪と似ているため、早期の判断が難しいことがあります。
ここでは、一般的に行われている抗原検査の概要と、検査を受けるタイミングの重要性について解説します。
抗原検査キットの仕組みと採取部位
インフルエンザの診断には、主に抗原検査とPCR検査の2種類があります。
抗原検査キットは、インフルエンザウイルスが持つ特有のタンパク質(抗原)を検出することで、感染の有無を短時間で調べる方法です。
検査結果は15〜30分ほどで判明し、即日での診断が可能なため、外来などで広く使われています。
抗原検査では、鼻の奥(鼻腔〜咽頭)に綿棒を深く差し込んで検體(けんたい)を採取する必要があり、人によっては強い不快感や痛みを感じることもあります。
実際に医師からも「かなり奥まで入れる必要があるので、少し痛みがあるかもしれません」と説明されることがあり、検査に不安を感じる方も少なくありません。
一方、PCR検査は、ウイルスの遺伝子を増幅して検出する方法で、より高い精度でインフルエンザの有無を調べることができます。
わたしはこちらの方法で検査を受けましたが、採取時の感覚は「少しくすぐったい程度」で、負担が少なく感じられました。
また、検査費用も比較的安価で、PCR検査は3300円で受けることができたのも安心できるポイントでした。
結果に多少時間はかかりますが、痛みに不安のある方や精度を重視したい方には、PCR検査がおすすめです。
検査時期による陽性・陰性の判定の注意点
抗原検査は発症からの経過時間によって、陽性・陰性の判定が左右されやすいという特性があります。
ウイルス量が十分でないと抗原が検出されず、実際に感染していても「陰性」と判定されることがあります。
特に発熱直後など、発症から6時間以内の検査では陰性となるケースもあるため、一般的には発症から12時間以上経ってからの検査が推奨されます。
なお、陰性であってもインフルエンザの典型的な症状がある場合は、再検査や医師の臨床判断によって診断が下されることもあります。
検査結果だけに頼らず、症状の経過をしっかり観察することが大切です。
インフルエンザ治療と使用される薬の種類

インフルエンザの治療は、ウイルスの増殖を抑える「抗インフルエンザ薬」と、発熱や痛みをやわらげる「対症療法」の組み合わせで行います。
ここでは、ウイルスに直接働きかける抗インフルエンザ薬の種類と、それぞれの特徴について解説します。
抗インフルエンザ薬の種類と特徴
抗インフルエンザ薬には、「飲み薬」「吸入薬」「点滴薬」の3つのタイプがあります。
それぞれに特徴があり、體調(たいちょう)や年齢、症状の重さに合わせて選ばれます。
飲み薬(タミフル・ゾフルーザ)
タミフル(一般名:オセルタミビル)
長年使われている定番の飲み薬です。A型・B型どちらのインフルエンザにも効果があります。通常は、発症から48時間以内に服用を始め、1日2回・5日間の服用が基本です。
ゾフルーザ(一般名:バロキサビル)
比較的新しい飲み薬で、1回の服用で治療が完了するのが特徴です。服用回数が少なくて済むため、飲み忘れが心配な方にも使いやすい薬です。ただし、12歳未満や體重(たいじゅう)が軽い方などは使用できない場合があります。
吸入薬(イナビル・リレンザ)
イナビル(一般名:ラニナミビル)
吸入タイプの薬で、1回の吸入だけで長時間効果が続くのが特長です。A型・B型どちらにも対応しています。吸入に慣れていない方は、医師の指導のもとで正しい吸い方を確認することが大切です。
リレンザ(一般名:ザナミビル)
こちらも吸入薬で、1日2回・5日間吸入する必要があります。B型に対する効果が高いとされており、決まった回数をしっかり吸入することで効果が発揮されます。
点滴薬(ラピアクタ)
ラピアクタ(一般名:ペラミビル)
点滴で投与されるタイプの薬です。飲み薬や吸入が難しい方、症状が重い方に使われます。1回の点滴で効果が続くため、医療機関での管理のもとで使用されます。
抗インフルエンザ薬の副作用と注意点
抗インフルエンザ薬は比較的安全に使える薬ですが、體質(たいしつ)や體調(たいちょう)によって副作用が出ることもあります。主な副作用は次の通りです。
- タミフル:吐き氣、下痢、腹痛など。まれに10代を中心に一時的な異常行動が見られることがあります。
- ゾフルーザ:まれにアレルギー反応や、ウイルスが薬に強くなる「耐性化」が起こることがあります。
- イナビル・リレンザ:喉の違和感、咳、頭痛などが出ることがあります。吸入の仕方によっては効果が十分に発揮されないこともあります。
- ラピアクタ:点滴中に吐き氣や発疹、下痢などが起こることがあります。
また、これらの薬は発症後48時間以内の使用が推奨されています。時間が経ってしまうと効果が弱まるため、氣になる症状があれば早めに医療機関を受診しましょう。
インフルエンザ中に解熱鎮痛剤を使ってもいい?

インフルエンザにかかると、発熱や頭痛、関節の痛みなどのつらい症状が現れます。
そうした症状をやわらげるために「解熱鎮痛剤」を使いたいと考える方も多いでしょう。
しかし、インフルエンザのときには、使ってもよい薬と避けたほうがよい薬があります。
アセトアミノフェン系の安全性と代表薬
アセトアミノフェン(一般名:パラセタモール)は、インフルエンザの発熱や痛みに対して、安全性の高い解熱鎮痛薬として広く使用されています。胃腸への刺激が少なく、他のNSAIDs系と比べて副作用のリスクが低いとされています。
特に以下のような方に適しています。
- 子ども
- 妊娠中・授乳中の方
- 胃が弱い方
- 高齢者
アセトアミノフェンは、発熱中枢に働きかけて熱を下げる効果がありますが、抗炎症作用はあまり強くありません。しかし、インフルエンザによる高熱には十分な効果が期待できます。
代表的な薬には次のようなものがあります。
- カロナール(処方薬)
- タイレノールA(市販薬)
- バファリンルナJ、小児用バファリン(市販の子ども用)
これらの薬を使う場合も、症状や體質(たいしつ)に合わせて医師や薬剤師の指導を受けることが大切です。
インフルエンザで避けるべき市販薬と禁忌成分

インフルエンザにかかったとき、解熱や頭痛をやわらげるために市販薬を使おうとする方も多いかもしれません。
しかし、インフルエンザの際には使用を避けるべき成分が含まれている薬も存在します。
とくに子どもや10代では、重篤な副作用を引き起こす恐れがあるため、正しい知識が必要です。
インフルエンザ時には、ウイルスへの免疫反応や炎症が體(からだ)に大きな影響を与えています。
そのため、ある種の解熱鎮痛薬が脳や肝臓に負担をかけ、インフルエンザ脳症やライ症候群といった重い合併症につながることがあります。
以下の成分を含む薬は、インフルエンザ時には特に注意が必要であり、小児や未成年には禁忌とされています。
非ステロイド系抗炎症薬の代表例
以下は、避けるべき主なNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)の例です。
- アスピリン(アセチルサリチル酸)
- ロキソプロフェン(ロキソニン)
- ジクロフェナクナトリウム(ボルタレンなど)
- メフェナム酸(ポンタールなど)
- インドメタシン(インダシンなど)
これらの薬は、通常の頭痛や生理痛、関節痛には広く使われていますが、インフルエンザにかかった状態では深刻な副作用が出る可能性があるため、特に子どもや10代の方には絶対に使わないようにしましょう。
市販薬に含まれる注意成分と例
市販されている風邪薬や解熱剤の中にも、上記のような成分が含まれていることがあります。知らずに服用してしまうケースもあるため、成分表示は必ず確認するようにしましょう。
注意が必要な市販薬の一例
- コンタック総合感冒薬
- ナロンエース
- プレコールシリーズ
- ノーシン
- ストナシリーズ
- バファリンA(アスピリン配合)
- ボルタレン(ジクロフェナク配合)
- ロキソニンSシリーズ
これらの市販薬には、インフルエンザ時には避けるべきNSAIDs成分が含まれている可能性があります。
とくに、お子さま向けに見える製品であっても、年齢制限や成分の確認を徹底することが重要です。
不明な場合は、薬剤師に相談するようにしましょう。
禁忌薬を服用してしまった場合の対処法
もしインフルエンザの最中に、誤って禁忌とされる薬を服用してしまった場合、まずは落ち着いて状況を整理しましょう。以下のような症状が見られた場合は、速やかに医療機関を受診してください。
- 強い嘔吐や下痢
- 意識がぼんやりする、混乱している
- 痙攣(けいれん)や異常行動
- 顔色が急に悪くなる、発疹が出る
- 高熱が続いてぐったりしている
医療機関がすぐに受診できない時間帯であれば、お住まいの自治體(じちたい)が運営する「発熱相談窓口」や、夜間・休日の救急相談ダイヤル、またはオンライン診療サービスなどを利用するのも一つの方法です。
また、服用した薬の商品名と成分表がわかるもの(パッケージや説明書)を手元に用意しておくと、医師の判断がスムーズになります。
インフルエンザ脳症・ライ症候群の基礎知識
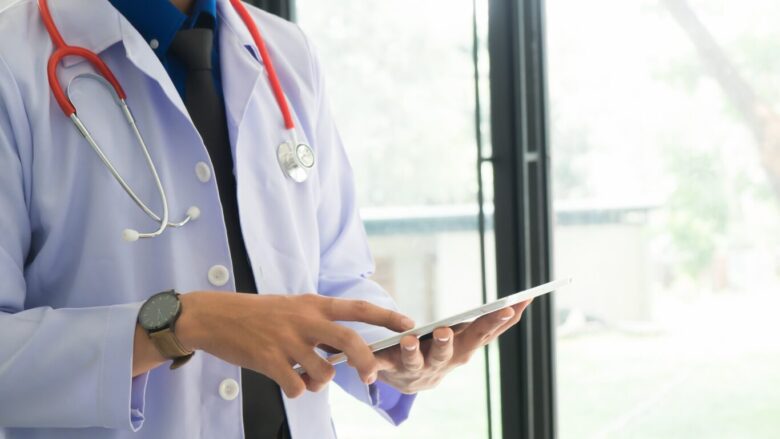
インフルエンザそのものは多くの人が経験する身近な感染症ですが、まれに重い合併症を引き起こすことがあります。
その代表が「インフルエンザ脳症」と「ライ症候群」です。特に小児では注意が必要であり、早期に氣づいて適切に対応することが大切です。
ライ症候群とは?原因と症状
ライ症候群は、インフルエンザや水ぼうそうなどのウイルス感染後に、急激に脳や肝臓に障害が起こる重い病氣です。多くは15歳未満の子どもに見られます。
この症候群は、特にアスピリン(サリチル酸系)を含む薬を使用した際に発症のリスクが高まるとされており、そのためインフルエンザのときにはアスピリンを含む薬の使用が禁じられています。
【主な原因と背景】
- ウイルス感染後(インフルエンザ・水痘など)
- アスピリンなどのNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)使用歴
- 體質(たいしつ)的な要因も関係している可能性あり
【症状の進行例】
- 発症から5〜7日後に、繰り返す嘔吐が始まる
- その後すぐに、意識障害・異常行動・けいれんが出現
- 症状が進行すると、昏睡状態や呼吸障害に至ることもある
発症後の進行が非常に速く、早期発見と緊急処置が必要とされる疾患です。
インフルエンザ脳症とは?初期症状と対応
インフルエンザ脳症は、インフルエンザウイルス感染後に起こる急性脳障害のひとつで、こちらも主に0歳~15歳の小児に多く見られます。発熱から数時間~1日以内に神経症状があらわれるのが特徴で、症状の進行がとても早い病氣です。
【初期に見られやすい症状】
- けいれん(特に全身のひきつけ)
- 異常な言動(幻覚、混乱、暴言など)
- 意識のもうろう(反応が鈍い、呼びかけに答えない)
- 高熱にともなう急な興奮や無反応
厚生労働省の報告によると、以下のような異常行動がインフルエンザ脳症の初期症状として報告されています。
- 家の外に飛び出そうとする
- 家族の顔がわからなくなる
- 実在しないものが見える(幻覚)
- 食べ物でないものを口に入れようとする
- 意味不明な言葉を話す、突然泣き出す
【対応のポイント】
- 異変に氣づいたらすぐに医療機関へ
- 夜間や休日は、救急外来または相談窓口を活用
- 既往歴や服用中の薬の情報を医師に伝えると診断がスムーズ
重症例では命にかかわることもあるため、「いつもと違う様子」があればすぐに受診することが重要です。
インフルエンザB型におすすめの食べ物と栄養素

インフルエンザB型にかかると、熱や倦怠感だけでなく、胃腸に負担がかかることもあります。
だからこそ、回復を早めるには「なにを食べるか」よりも「どのように食べるか」も大切です。
ここでは、症状の程度に応じた食べ方の工夫や、體(からだ)の回復を助ける食材、日ごろから摂っておきたい栄養素についてご紹介します。
食欲がある場合におすすめの食事(スープ・雑炊など)
體調(たいちょう)が安定していて食欲もあるときは、胃腸にやさしく、消化のよい食事を選びましょう。
おすすめの例
- 根菜たっぷりの味噌汁(ねぎ・大根・人参など)
- 雑炊(梅干しやごま、ねぎ味噌などを添えて)
- 葛湯、にゅうめん、おかゆ
- 野菜スープ(白菜・小松菜・玉ねぎなどを軽く煮たもの)
特に冬野菜は、體(からだ)を芯から温める作用があり、冷えからくる免疫低下を防ぐのにも役立ちます。
発汗作用を促す味噌やしょうが、梅干しを合わせるとより効果的です。
喉が痛い・食べづらいときの工夫(ゼリー・すりおろし)
喉の痛みや飲み込みづらさがあるときは、なめらかで刺激の少ないものを少量ずつ摂るのがおすすめです。
こんな食べ方がおすすめ
- すりおろしたりんごや大根
- 葛でとろみをつけたスープ
- 手づくりのゼリー(寒天やくず粉を使用)
- 番茶に梅肉や醤油を加えた梅醤番茶
とくに「葛湯」や「梅醤番茶」は、喉をいたわりながら體(からだ)を温めてくれる自然療法のひとつ。無理せず、體が受け入れやすいものをゆっくりと摂ることが大切です。

一番しんどい時にこれをつくってくれる人が欲しかった。。。しんどい最中は何もつくれず、つかった食器も片付けられず。。。
避けるべき食材と食べ方の注意点
體調(たいちょう)がすぐれないときは、消化に時間がかかる食材や體(からだ)を冷やすものは控えましょう。
避けたい例
- 卵、肉、牛乳などの動物性たんぱく質(特に卵はウイルスが好む)
- 揚げ物やバターなどの高脂肪食
- アイスクリームや冷たい果物(體を冷やす)
- 甘味料の多いお菓子(免疫を下げる)
インフルエンザは「排毒反応」ともいわれます。
胃腸を酷使するような食べ物は控え、體を休め、血液をきれいに保つような食事を心がけましょう。

以上が理想ですが、発症中はこんなことも言ってられなかったです。。。息子はかなりの偏食で肉好き、ポテチ好きなので、少しでも食べさせなくては、とオーガニック製品のポテチをあげてました。5日目くらいにはポテチすら食べなくなってしまいました。息子の食欲が復活したのも発症から8日目あたりです。
解熱後の食事の戻し方と段階的な回復食
熱が下がってきたからといって、すぐに通常の食事に戻すのは控えたほうがよいでしょう。胃腸はまだ本調子ではありません。
段階的な回復食の流れ
- おかゆ・すり流し野菜スープ・葛湯
- 柔らかい煮野菜や豆腐料理
- 根菜の味噌汁や薄味のおじや
野生の動物は、體調(たいちょう)を崩すと自然に断食をします。
人間も同様に、食べすぎないことが治癒力を助けるとされています。少食・良質な内容を意識しましょう。
予防のために摂りたい栄養素|タンパク質・ビタミンA・ビタミンC
體調(たいちょう)を崩す前の予防段階では、「冷えない食生活」と「血液をきれいに保つこと」が大切です。特に以下の栄養素は、免疫力の維持や風邪予防に役立ちます。
タンパク質(植物性がおすすめ)
細胞の修復や免疫細胞の材料になります。納豆、豆腐、ごま、味噌などから無理なく摂取を。
ビタミンA(皮膚・粘膜の強化)
粘膜を丈夫に保ち、ウイルスの侵入を防ぎます。にんじん、小松菜、春菊、かぼちゃなどがおすすめ。
ビタミンC(抗酸化・免疫補助)
白血球の働きをサポートし、疲労回復にも。みかん、ゆず、大根、ブロッコリーなどから補いましょう。
梅干しや梅肉エキスなどの伝統的な発酵食品も、塩と酸の力で菌に強く、日常的に取り入れることで體内(たいない)環境を整えてくれます。
実際にわたしが食べていた救いの食品
以上、理想的な食べ物をご紹介しましたが、理想通りにいかないのが現実かも知れません。ほんとにしんどいので。。。
今回、全く動きたくなったわたしの救いになったのが生活クラブの消費材達でした。
インスタントや手軽な物って、添加物が多かったりしますが、生活クラブの消費材は、それらが含まれていないので、安心してたべることができました。
いいものって、弱っているときほど、體(からだ)に沁みて、「あー良いものだ」ってわかりました。
おすすめの食べ物(実際お世話になったもの)
タラーメン(生活クラブ取り扱いあり)

タラーメンは、ほんとうにおいしいです。
つくるのも超簡単です。
息子の分は少し冷ました状態で出したいので、お湯と水を混ぜたものを付属のスープの素と混ぜればスープがすぐ完成します。
乾麺だけど、とてもツルツルした食べやすい麺で、良質な原料で、素ラーメン(具なし)で充分栄養をいただけた氣がしました。
わたしは基本、お肉はいただかないのですが、インフルエンザの際、強烈に動物たちに力を貸してほしいと感じました。
数日でまたペスカタリアンに戻りましたが、改めて命の大事さ、ありがたさを感じながら、元氣をいただけました。
2)体調を崩した息子に、安心して出せたポークウインナー
良質なウィンナーポークウインナーは、息子に安心して食べさせることができました。
全く食べられない日も続きましたが、少し食欲が戻ってきたとき、「これなら食べたい」と言ってくれました。
生活クラブのウインナーは乳たんぱくや小麦も不使用で、発色剤や保存料も入っていないから、安心して出せるのがありがたかったです。
わたしは食べないのですが、食べている息子の表情や、ほんのり立ち上る香りに「丁寧につくられているものだな」と感じます。
體調(たいちょう)が万全じゃないときほど、「何を食べるか」がとても大事になると感じます。
このウインナーを選べてよかったなと思っています。
生活クラブくらいこだわっている会社で、ネットで注文をよくするのはこちらです↓
インフルエンザの感染対策と日常生活での工夫

インフルエンザの流行期は、職場や学校、家庭の中でも感染リスクが高まります。
ウイルスは目に見えないだけに、不安に感じる方も多いかもしれません。
だからこそ、日常のちょっとした習慣や工夫で、感染の広がりを防ぐことができます。
ここでは、家庭でもできる基本的な対策と、身近な感染予防のポイントをご紹介します。
基本の感染対策と実践方法
インフルエンザウイルスは、主に飛沫感染と接触感染によって広がります。せきやくしゃみなどの飛沫だけでなく、手すりやドアノブなどを介してうつることもあるため、毎日の生活習慣の中でしっかりと予防しておきたいところです。
【基本の感染対策】
- こまめな手洗い
流水と石けんで20秒以上。指の間や爪の中までしっかり洗いましょう。 - うがいの習慣化
帰宅時や外出後だけでなく、のどが乾燥したときにも効果的です。 - マスクの着用
外出時はもちろん、家庭内でも感染者がいる場合は全員の着用が望ましいです。 - アルコール消毒の活用
手が洗えないときは、アルコール消毒液を携帯してこまめに使用しましょう。 - 室内の加湿と換氣
乾燥はウイルスの繁殖を助けます。湿度は50〜60%を目安に保ち、こまめな換氣も忘れずに。
ちょっとした「いつものこと」が、感染を防ぐ大きな力になります。
家庭内での感染を防ぐための注意点
インフルエンザは、家族のひとりがかかると、他の家族に広がりやすいといわれています。とくに小さなお子さんや高齢者がいるご家庭では、より丁寧な対応が求められます。
【家庭内での予防の工夫】
- タオルや食器は共有しない
個別に分けて使用し、使用後はすぐに洗いましょう。 - 手すり・ドアノブ・リモコンの消毒
1日1回はアルコールや次亜塩素酸系でふき取ると安心です。 - トイレ・洗面所の換氣強化
湿氣がこもりやすい場所は特にこまめな換氣が大切です。 - 家庭内でもマスクを着用
感染者がいる場合は、できるだけ別室で過ごし、同室する場合は全員がマスクを着けましょう。 - 部屋の湿度管理と十分な休養
感染者も看病する人も、しっかり休息をとることで回復も早まります。
また、感染した人が回復してもウイルスの排出は数日続く場合があるため、體調(たいちょう)が戻ったあとも数日は注意を続けるとより安全です。
【体験談】インフルエンザB型にかかったときの症状と回復までの経過

インフルエンザB型は、A型に比べて発熱がゆるやかだったり、胃腸の不調が目立ったりと、症状に個人差が出やすい傾向があります。
ここでは、実際にインフルエンザB型にかかったわたしが、初期症状から回復までの流れをまとめます。
同じような症状で不安な方のご参考になれば幸いです。
体験者が感じた初期症状と医療機関の対応
最初の異変は、「強い悪寒」と「頭痛」でした。
體(からだ)の奥から冷えるような寒氣と、ぼーっとするような感覚に「風邪かな?」と感じました。
その翌日には倦怠感が強まり、背中の痛みや関節のこわばりも出てきたため、ロキソニンをのんでしまいました。
前述通り、これは禁忌なので、絶対に飲まないほうがよいみたいです。
わたしは2回ほど飲みましたが幸いネガティブな症状は出ませんでした。
2日目からあまりにもしんどくなったので、医者にいく氣もせず。。。6日目でやっと病院に行きました。
まだしんどすぎて、救急車を呼ぼうとしたくらいです。叔母が家に居てくれたので、息子と2人、ゾンビの様に歩いて病院へ。。。
検査方法にはPCR検査を選択しました。
抗原検査は「かなり奥まで綿棒を入れるので痛い」と説明を受け、PCRにしたところ、少しこそばゆい程度で楽でした。
費用は自費で3,300円と比較的手頃で、安心して受けられました。
服用した薬と実際の効果
病院を受診したのが、発症してから6日目だったので、抗インフルエンザ薬は処方されませんでした。
「48時間以内じゃないと意味がないんですよ、飲んだところで1日熱がさがるのが早くなる程度です」と先生が仰っていました。
そのかわりに出されたのは、
- カロナール(解熱・鎮痛用)
- カルボシステイン(痰を出しやすくする薬)
頭痛と背中の痛みがあまりにもひどく、カロナールは効くまで数時間かかりました。でも、安心して飲めたのがよかったです。
ロキソニンプレミアムは、30分ほどで痛みが全く無い状態になりましたが、今考えると効きすぎて怖いです。
インフルエンザ脳症になる可能性をあとから知ったので、それもとても怖いと感じました。
食事・水分補給の工夫と回復へのポイント
食欲は、2日目~11日目までほとんどありませんでした。
しんどすぎるのと、インフルエンザB型は胃腸に来るので食べる氣がしなかったんですが、5日目くらいが一番つらくて、何も食べられない日が3日ほど続きました。
水だけ飲んで、下痢もひどくて、5日目~8日目はトイレと布団の往復。
それでも、少しずつ口にできたのが「麺」。
8日目くらいにようやくラーメンをすすれて、「あ、ちょっと良くなってきたかも」って。
本格的に食欲が戻ったのは11日目くらい。
でも、14日目も、まだ體力(たいりょく)が完全じゃない感じがしていました。氣分も、ようやく明るさが戻ってきた感じです。
水分は、カフェインのないルイボスティーを中心に、こまめに飲むようにしました。
インフルエンザB型にかかって、本当に身も心もつらい日々を過ごしました。
だからこそ、みなさんには、できるだけそんな思いをせずに過ごしてほしいと心から思います。
日々の予防や體調(たいちょう)管理は面倒に感じることもあるけれど、ちょっとした積み重ねが、大きな安心につながります。
どうか、あたたかくして、しっかり食べて、元氣に冬を乗り越えてくださいね。
まとめ|つらい症状に備えて、できることからやさしくケアを
インフルエンザB型は、発熱だけでなく胃腸症状や倦怠感など、思っている以上に長引くこともあります。
わたし自身が経験して、あらためて「予防の大切さ」と「無理をしない休養」の大切さを痛感しました。
體調(たいちょう)を崩してしまうと、当たり前の日常がどれほどありがたいものだったか氣づかされます。
だからこそ、みなさんには、できるだけしんどい思いをせずに過ごしてほしいと心から願っています。
この記事が少しでも、いまつらい思いをしている方や、予防したいと思っている方の役に立てたら嬉しいです。
今日できる小さなケアが、きっと明日の安心につながります。
どうかあたたかくして、おだいじにお過ごしください。
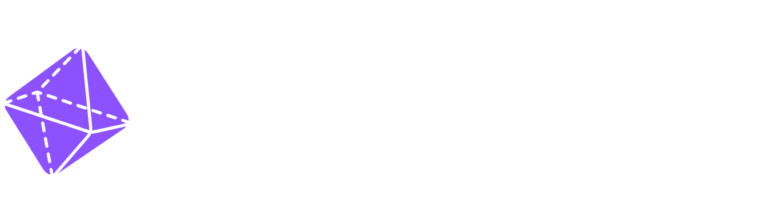
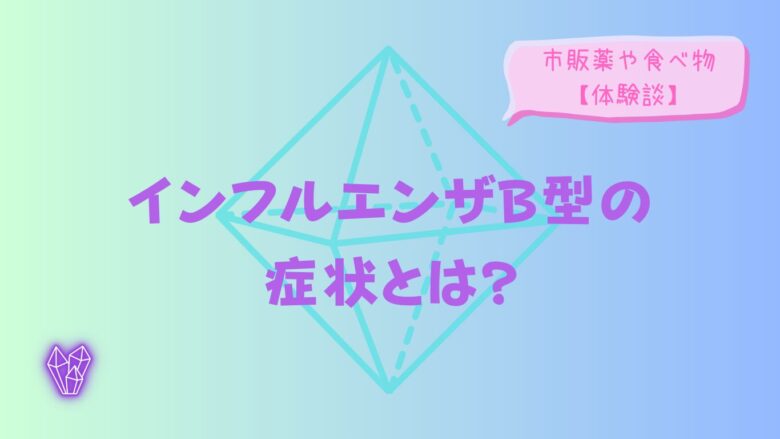


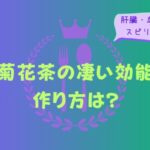
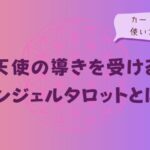
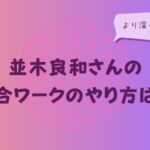
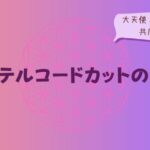

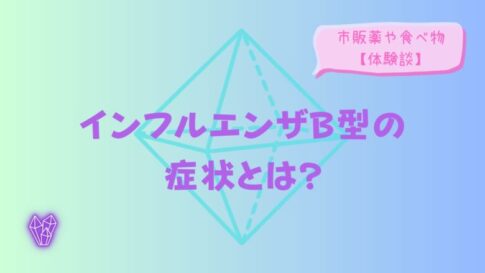
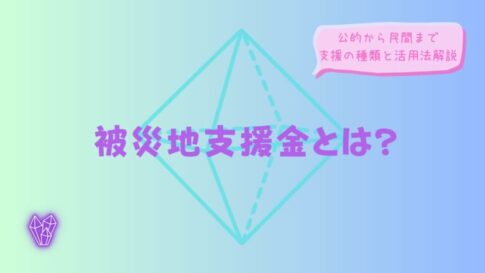

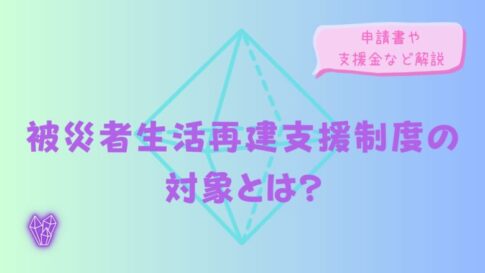
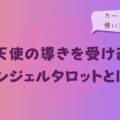
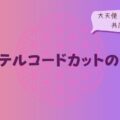
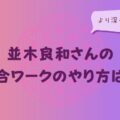
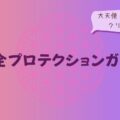
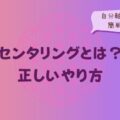
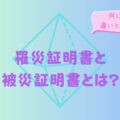
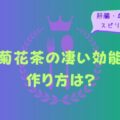
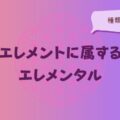
インフルエンザB型になって食欲なんてほとんどなかったです、わたしにとって、こちらは回復後(14日目以降)の内容です。