地震や津波などの大規模災害でマンションが甚大な被害を受けた場合、再建や売却の手続きには多くの課題が伴います。
「被災マンション法」は、そうした状況でも迅速に対応できるよう特別な決議手続きを定めた法律です。
本記事では、適用条件や具體的(ぐたいてき)な手続きを詳しく解説し、被災マンションの再生方法を分かりやすく紹介します。災害時に備え、ぜひ知っておきたい情報です。
もくじ
被災マンション法とは?

マンションが地震や津波などの災害で甚大な被害を受けたとき、住民は再建や売却を考えます。しかし、通常の法律では全員の同意が必要になり、一人でも反対すると再建が進まないという問題がありました。こうした課題を解決するために生まれたのが「被災マンション法」です。
この法律では、一定の条件を満たすマンションに対し、5分の4以上の賛成で再建や売却の決議を進められる特例が設けられています。被災後の住民の負担を軽減し、できるだけ早く新たな生活を築けるよう支援するのが目的です。
「もし自分のマンションが被災したら…」と考えると不安になるかもしれませんが、適用条件や手続きの流れを知っておくことで、いざというときに慌てずに済みます。
ここからは、被災マンション法の背景や適用条件について詳しく解説していきます。
被災マンション法の制定背景と目的
この法律が生まれたきっかけは、阪神・淡路大震災です。1995年1月17日に発生した大震災では、多くのマンションが倒壊し、住民は再建や売却の問題に直面しました。しかし、区分所有法では全員の同意が必要なため、意見が合わずに長期間放置されるマンションが多く発生しました。
そこで、特例を設けて決議を進めやすくするために「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)」が制定されました。この法律により、5分の4以上の賛成があれば、建物の再建や敷地の売却が可能になり、迅速な対応が取れるようになりました。
さらに、2011年の東日本大震災を受けて、法律が改正されました。この改正により、マンションが「一部損壊」した場合でも、5分の4以上の賛成があれば建物の取り壊しや売却が可能となり、より柔軟な対応ができるようになったのです。
この法律があることで、住民は被災後の生活再建に向けた選択肢を持てるようになりました。では、どのような災害が適用対象になるのでしょうか?
適用される災害の種類と条件
被災マンション法が適用されるのは、国が「政令指定災害」と認定したケースに限られます。これは、単なる小規模な被害ではなく、広範囲にわたって甚大な影響を及ぼす災害を指します。具體的(ぐたいてき)には、以下のような災害が対象です。
- 地震(阪神・淡路大震災、東日本大震災など)
- 津波(東日本大震災による津波被害など)
- 豪雨や水害(西日本豪雨、台風による洪水など)
これらの災害によって、マンションが全部滅失(全壊)した場合、または大規模一部滅失(価値の半分以上が失われた場合)には、被災マンション法が適用されます。
被災マンション法の適用範囲

被災マンション法が適用されるのは、すべての被災マンションではなく、特定の条件を満たした場合のみです。マンションの損壊状況や災害の種類によって、適用されるかどうかが決まります。
ここでは、全部滅失と大規模一部滅失の違い、法律の適用条件、そして通常の区分所有法との違いについて詳しく解説します。
「全部滅失」と「大規模一部滅失」の違い
被災マンション法が適用されるには、マンションが「全部滅失」または「大規模一部滅失」のいずれかに該当する必要があります。この二つは似ているようで、法律上の扱いが異なります。まずは、それぞれの違いを理解しておきましょう。
全部滅失とは
マンション全體(ぜんたい)が倒壊したり、火災や津波などで建物としての機能を完全に失った状態を指します。たとえば、大地震で建物が崩れ落ちたり、津波で基礎部分から流されたりしたケースがこれに該当します。
この場合、建物が消滅するため、区分所有権もなくなります。通常、マンションの再建や敷地の売却には所有者全員の合意が必要になりますが、被災マンション法が適用されると、五分の四以上の賛成があれば決議が可能になります。
大規模一部滅失とは
マンション全體(ぜんたい)が倒壊していなくても、建物の価格の二分の一以上が失われるような損害を受けた場合が該当します。たとえば、地震によって一部の階が崩壊したり、火災で主要な部分が焼失した場合などが考えられます。
この場合、区分所有権は存続しますが、通常の区分所有法では建物の取り壊しや売却には全員の同意が必要になります。しかし、被災マンション法を適用すれば、五分の四以上の賛成で建物の取り壊しや敷地の売却を決めることができます。
被災マンション法が適用されるマンションの条件
この法律は、すべての被災マンションに適用されるわけではなく、一定の条件を満たした場合にのみ適用されます。
- 政令指定災害による被害であること
- 建物が全部滅失または大規模一部滅失していること
- 区分所有建物であること
- 被災マンション法の適用が宣言されること
地震や津波などの大規模災害であっても、被害の程度が軽微な場合や政令指定を受けていない災害は適用外となります。また、戸建て住宅や賃貸マンションは対象外となり、あくまで区分所有建物に限られます。
マンションの再建や売却を迅速に進めるには、この法律の適用を受けることが大きな助けになります。ただし、適用されるためには、マンションの状態や災害の種類が重要なポイントとなることを覚えておきましょう。
区分所有法との違い
マンションの管理や意思決定には通常、区分所有法が適用されます。しかし、被災マンション法は区分所有法とは異なる特例法として機能し、意思決定のルールが大きく異なります。
| 項目 | 被災マンション法 | 区分所有法 |
|---|---|---|
| 適用対象 | 政令指定災害で被災したマンション | 一般的なマンション |
| 適用条件 | 全部滅失または大規模一部滅失 | 通常の修繕や建て替え時 |
| 再建・売却の決議要件 | 五分の四以上の賛成で決議可能 | 全員の同意が必要 |
| 区分所有権 | 全部滅失時に消滅 | 存続し続ける |
| 取り壊し・売却 | 五分の四以上の賛成で決定可 | 全員の同意が原則 |
最大の違いは、意思決定のハードルの高さにあります。区分所有法では、建て替えや売却を進めるために全員の合意が必要になりますが、被災マンション法では五分の四以上の賛成で決議できるため、スムーズな対応が可能になります。
また、全部滅失の場合、区分所有権自體(じたい)がなくなるため、法律上は「マンションが存在しない状態」となります。そのため、新しいルールに基づいて再建や売却の判断を行う必要があります。
この法律が適用されることで、被災したマンションの住民が迅速に次の生活へ進めるようになり、災害後の混乱を最小限に抑えることができます。
全部滅失の場合の手続き

マンションが災害によって完全に倒壊し、建物としての機能を失った場合、それまでの区分所有権も消滅します。通常のルールでは、再建や敷地の売却には所有者全員の同意が必要ですが、被災マンション法の適用により、5分の4以上の賛成があれば意思決定が可能になります。
ここでは、建物を再建する場合や敷地を売却する場合の具體的(ぐたいてき)な手続きについて解説します。
建物の再建手続き
マンションを再建する場合、まず再建決議を行う必要があります。この決議では、新しいマンションの設計や費用分担について話し合い、一定の賛成が得られた場合に再建が進められます。
再建の流れは以下の通りです。
- 敷地共有者による集会の開催
- 再建の可否を決めるための会議を開く必要があります。
- 集会の招集は、管理者または敷地共有者の5分の1以上の議決権を持つ者が行います。
- 再建決議の実施
- 5分の4以上の賛成があれば再建が決定されます。
- 再建する建物の設計概要や建築費用、費用負担の割合なども決めます。
- 再建に参加しない共有者への対応
- 再建決議に反対した人や参加しない人に対し、敷地を売却するかどうかの確認を行います。
- 2か月以内に回答がない場合、再建に参加しないものとみなされます。
- 再建資金の調達と工事開始
- 再建のための資金を調達し、具體的(ぐたいてき)な建築計画を進めていきます。
- 参加しない共有者の権利は、再建に参加する者が時価で買い取ることができます。
マンションを再建することで、住民はもとの場所に住み続けることができますが、建築費用の負担が発生するため、事前に資金計画を立てることが重要です。
敷地の売却手続き
マンションを再建せずに敷地を売却する場合は、敷地売却決議を行い、一定の賛成が得られれば売却が進められます。
敷地の売却手続きの流れは以下の通りです。
- 敷地共有者による集会の開催
- 売却の是非を決めるための会議を開きます。
- 再建決議と同様に、管理者または敷地共有者の5分の1以上の議決権を持つ者が招集します。
- 敷地売却決議の実施
- 5分の4以上の賛成があれば売却が決定されます。
- 売却先や売却価格の見込みについても話し合います。
- 売却に参加しない共有者への対応
- 売却に反対した人や参加しない人に対し、権利を売却するかどうかの確認を行います。
- 2か月以内に回答がない場合、売却に参加しないものとみなされます。
- 売却契約の締結と代金分配
- 買い手が決まり次第、売却契約を締結し、代金を敷地共有者に分配します。
敷地の売却を選択することで、住民は新たな生活の資金を得ることができます。ただし、売却価格によっては再建する場合よりも経済的な負担が少なくなる場合とそうでない場合があるため、慎重に検討する必要があります。
再建決議とその要件
再建決議とは、マンションを再建するかどうかを決めるための手続きであり、敷地共有者の5分の4以上の賛成が必要となります。
再建決議で決めるべき主な事項は以下の通りです。
- 再建する建物の設計概要
- 建築費用とその分担方法
- どの部分を誰が所有するか
再建決議が成立すると、決議に反対した敷地共有者に対し、2か月以内に売却に参加するかどうかの意思を確認する手続きが必要になります。売却に参加しない場合、再建に参加する者がその権利を時価で買い取ることができます。
敷地売却決議とその要件
敷地売却決議とは、マンションを再建せずに敷地を売却するかどうかを決めるための手続きで、敷地共有者の5分の4以上の賛成が必要となります。
敷地売却決議で決めるべき主な事項は以下の通りです。
- 敷地の売却先
- 売却価格の見込み
- 売却による代金の分配方法
敷地売却決議が成立すると、売却に参加しない敷地共有者に対し、売却に応じるかどうかの意思確認を行います。2か月以内に回答がない場合、売却に参加しないものとみなされます。
その後、敷地の買い手が決まれば売却契約を締結し、代金が敷地共有者に分配されます。売却に参加しない共有者の権利については、売却に参加する者が時価で買い取ることができます。
大規模一部滅失の場合の手続き

マンションの一部が損壊した場合でも、被害の程度によっては住み続けることが困難になることがあります。特に、建物の価格の半分以上が失われた「大規模一部滅失」に該当する場合、再建や売却をスムーズに進めるために、被災マンション法が適用されます。
大規模一部滅失では、マンションの復旧、建て替え、売却、取り壊しのいずれかを選択することになります。通常の区分所有法では全員の同意が必要ですが、被災マンション法を適用すれば、5分の4以上の賛成で意思決定が可能になります。
ここでは、それぞれの手続きの流れについて解説します。
建物の復旧決議
マンションを引き続き使用するためには、復旧工事を行う必要があります。復旧決議では、どのような修繕を行い、どの程度の費用が必要なのかを話し合います。
復旧の流れは以下の通りです。
- 管理組合による集会の開催
- 復旧の可否を決めるために、区分所有者による会議を開きます。
- 集会の招集は、管理者または区分所有者の5分の1以上の議決権を持つ者が行います。
- 復旧決議の実施
- 5分の3以上の賛成があれば復旧が決定されます。
- 復旧の範囲や修繕費用、費用の負担方法などが決められます。
- 復旧工事の開始
- 修繕のための工事計画を立て、工事が始まります。
復旧を選択すれば、現在の建物をできるだけ活かしながら生活を続けることができます。ただし、耐震性の低下や再発リスクを考慮し、慎重に判断する必要があります。
建物の建て替え決議
復旧では対応できない場合や、建物の損傷が著しい場合には、建て替えを選択することも可能です。
建て替えの流れは以下の通りです。
- 管理組合による集会の開催
- 建て替えの是非を決めるために、区分所有者による会議を開きます。
- 集会の招集は、管理者または区分所有者の5分の1以上の議決権を持つ者が行います。
- 建て替え決議の実施
- 5分の4以上の賛成があれば建て替えが決定されます。
- 新しい建物の設計、建築費用、費用の負担方法などが決められます。
- 建て替えに参加しない所有者への対応
- 決議に反対した人や参加しない人に対し、権利を売却するかどうかの確認を行います。
- 2か月以内に回答がない場合、建て替えに参加しないものとみなされます。
- 建築計画の進行と工事開始
- 資金の調達と工事のスケジュールを確定し、建て替えを開始します。
建て替えを選択することで、新しい建物に住むことができますが、費用負担が大きくなるため、所有者間で十分に話し合う必要があります。
建物・敷地の売却手続き
復旧や建て替えが困難な場合、マンションの建物と敷地を売却することも選択肢の一つです。
売却の流れは以下の通りです。
- 区分所有者による集会の開催
- 売却の是非を決めるための会議を開きます。
- 集会の招集は、管理者または区分所有者の5分の1以上の議決権を持つ者が行います。
- 建物・敷地売却決議の実施
- 5分の4以上の賛成があれば売却が決定されます。
- 売却先や売却価格の見込みについても話し合います。
- 売却に参加しない所有者への対応
- 売却に反対した人や参加しない人に対し、権利を売却するかどうかの確認を行います。
- 2か月以内に回答がない場合、売却に参加しないものとみなされます。
- 売却契約の締結と代金分配
- 買い手が決まり次第、売却契約を締結し、代金を区分所有者に分配します。
売却を選択することで、新しい生活を始める資金を得ることができますが、市場価格によっては期待通りの金額を得られない可能性もあるため、慎重な判断が求められます。
建物の取り壊しと敷地売却手続き
マンションをそのまま売却するのではなく、建物を取り壊してから敷地を売却する方法もあります。
取り壊しと売却の流れは以下の通りです。
- 区分所有者による集会の開催
- 取り壊しと売却の是非を決めるための会議を開きます。
- 集会の招集は、管理者または区分所有者の5分の1以上の議決権を持つ者が行います。
- 取り壊しと敷地売却決議の実施
- 5分の4以上の賛成があれば決議が成立します。
- 取り壊しの費用負担や敷地売却の条件などを決めます。
- 売却に参加しない所有者への対応
- 反対した人や参加しない人に対し、権利を売却するかどうかの確認を行います。
- 2か月以内に回答がない場合、売却に参加しないものとみなされます。
- 取り壊しと売却の実施
- 建物を取り壊し、敷地を売却する契約を締結します。
- 売却による代金を区分所有者に分配します。
取り壊しを選択することで、土地としての価値を最大限に活用しやすくなりますが、取り壊し費用が発生するため、事前にコストを検討することが重要です。

大規模一部滅失の場合、復旧、建て替え、売却、取り壊しのいずれかを選択することになります。被災マンション法を活用することで、所有者全員の同意が得られない場合でも、5分の4以上の賛成があれば迅速に対応することが可能になります。
どの選択肢を選ぶべきかは、建物の損傷状況や費用負担のバランス、住民の意向によって異なります。次の章では、被災マンション法による意思決定の流れについて詳しく解説します。
被災マンション法による意思決定の流れ
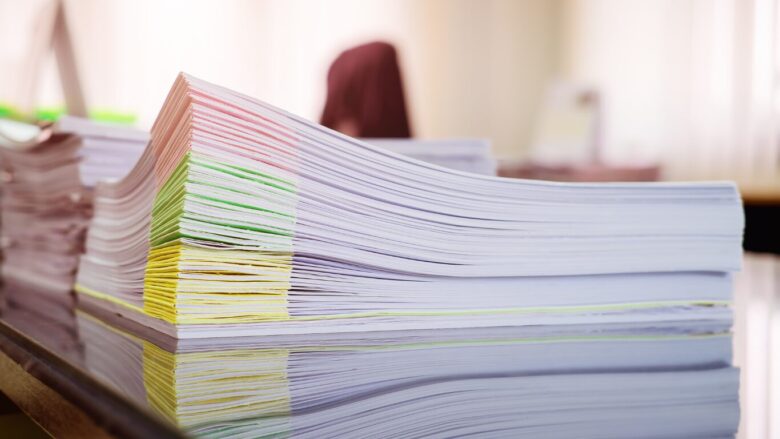
被災マンション法では、マンションの再建や売却を進める際に、どのような意思決定を行うかが重要になります。特に、災害が発生した直後と、政令で指定された後では、決議の要件が変わります。
この章では、政令指定前後の決議要件の違い、5分の4以上の賛成が必要なケース、全員合意が必要なケースについて詳しく解説します。
政令指定前の決議要件
被災マンション法では、マンションの再建や売却を進める際に、どのような意思決定を行うかが重要になります。特に、災害が発生した直後と、政令で指定された後では、決議の要件が変わります。
この章では、政令指定前後の決議要件の違い、5分の4以上の賛成が必要なケース、全員合意が必要なケースについて詳しく解説します。
政令指定後の決議要件
国が被災地域を政令指定すると、被災マンション法が適用され、特例が認められるようになります。これにより、通常は全員の同意が必要な決議でも、一定の賛成が得られれば手続きを進めることが可能になります。
政令指定後の決議要件は以下の通りです。
- 建物の再建 → 5分の4以上の賛成で決議可能
- 敷地の売却 → 5分の4以上の賛成で決議可能
- 建物の取り壊し → 5分の4以上の賛成で決議可能
- 建物と敷地の一括売却 → 5分の4以上の賛成で決議可能
政令指定を受けることで、決議のハードルが大きく下がり、より迅速に再建や売却の手続きを進めることができるようになります。
5分の4以上の賛成が必要なケース
被災マンション法が適用されると、全員の合意がなくても決議が可能になります。ただし、そのためには5分の4以上の賛成が必要です。
5分の4以上の賛成が必要なケースは以下の通りです。
- マンションの再建
- 再建する建物の設計や建築費用の分担を決定する際にも適用されます。
- 敷地の売却
- 被災したマンションを解體(かいたい)し、土地のみを売却する場合も5分の4以上の賛成が必要です。
- 建物の取り壊しと敷地売却
- 建物を取り壊し、その後に敷地を売却する場合も同様です。
- 建物と敷地の一括売却
- 再建せずに、建物と敷地をそのまま売却する場合も5分の4以上の賛成が求められます。
5分の4以上の賛成が必要な決議は、通常の区分所有法では全員の合意が必要だったものばかりです。被災マンション法の適用によって、迅速な復旧が可能になることが最大のメリットと言えます。
全員合意が必要なケース
被災マンション法が適用されても、全員の合意が必要なケースも存在します。
全員合意が必要なケースは以下の通りです。
- 被災マンション法の適用前に意思決定を行う場合
- 政令指定前は通常の区分所有法が適用されるため、再建や敷地の売却には全員の合意が必要です。
- 個別の専有部分の権利変更を伴う決議
- 例えば、建物を再建する際に所有者の区画を変更する場合などは、全員の合意が必要になることがあります。
- 個別の補償や賠償に関する合意
- 例えば、再建や売却に参加しない住民に対する補償を決める場合などは、関係するすべての住民の合意が求められることがあります。
全員合意が必要なケースは少ないものの、一定の条件下では引き続き全員の意思を確認しなければならないこともあるため、注意が必要です。

被災マンション法では、政令指定を受けることで、従来の区分所有法よりもスムーズに意思決定を進めることができます。特に、5分の4以上の賛成があれば、再建や売却が可能になる点が大きな特徴です。
ただし、全員の合意が必要なケースも一部存在するため、状況に応じた判断が求められます。被災後のマンションの対応には、法律の適用範囲を正しく理解し、住民同士でしっかりと話し合うことが大切です。
被災マンション法の改正点

被災マンション法は、1995年の阪神・淡路大震災を受けて制定されましたが、その後の東日本大震災をきっかけに、2013年に改正が行われました。この改正により、マンションが「大規模一部滅失」した場合でも、5分の4以上の賛成で建物の取り壊しや敷地売却が可能となり、より柔軟な対応ができるようになりました。
ここでは、2013年の改正内容と、それによる影響や実施事例について解説します。
2013年の改正内容
東日本大震災では、マンションが「全部滅失」したケースだけでなく、「一部が損壊したものの、住み続けるには危険な状態」のケースも多く発生しました。しかし、改正前の被災マンション法では、マンションの「全部滅失」のみを対象としており、大規模な損壊を受けても建物が残っている場合は適用されませんでした。
そのため、建物が大きく損傷しても取り壊しの決議が進められないといった問題が発生しました。これを受けて、2013年の改正では、以下の点が追加されました。
- 「大規模一部滅失」の場合でも、5分の4以上の賛成があれば取り壊しや敷地売却が可能に
- 建物と敷地をまとめて売却する決議ができるように
- 決議要件の明確化と手続きの簡素化
これにより、全部滅失していなくても、建物の価値が大幅に失われたり、安全性が確保できない場合は、被災マンション法を適用して対応できるようになりました。
改正による影響と実施事例
2013年の改正によって、実際にいくつかの被災マンションが迅速に対応を進めることができました。
1. 東日本大震災による被災マンションの取り壊し決議
東日本大震災では、津波の被害により建物の基礎部分が損壊し、居住が難しくなったマンションが多数発生しました。しかし、建物が一部残っていることで、区分所有法の制約により取り壊しが進まないケースもありました。
2013年の改正後、これらのマンションの多くが5分の4以上の賛成を得て取り壊し決議を行い、土地を売却することで問題を解決しました。特に、仙台市や福島県の沿岸部では、この法律の適用により、被災マンションの処理がスムーズに進められた事例がいくつか報告されています。
2. 熊本地震での適用事例
2016年の熊本地震でも、大規模なマンションの被害が発生しました。中には、建物の一部が大きく損壊したものの、全壊ではないため、法律の適用が難しいケースもありました。
しかし、2013年の改正によって、「大規模一部滅失」の状態でも5分の4以上の賛成があれば取り壊しが可能になったため、複数のマンションでスムーズに再建や売却の決議が進められました。この改正がなければ、所有者全員の合意が必要となり、長期間放置される恐れがあったと考えられます。
3. 首都圏の老朽マンションにも影響
被災マンション法の改正は、自然災害だけでなく、老朽化したマンションの対応にも影響を及ぼしました。特に、耐震性に問題があるマンションでは、地震などの災害によって一部が損壊した場合、迅速に取り壊しや売却の決議ができるようになりました。
例えば、東京都内のあるマンションでは、建物の一部が地震で損傷し、居住者の安全を確保するために取り壊しを決定。しかし、従来のルールでは全員の合意が必要であったため、進展が難しかったところ、2013年の改正によって、5分の4以上の賛成で速やかに決議が成立し、敷地売却が実現しました。

2013年の被災マンション法の改正により、災害によるマンションの対応がより柔軟になりました。特に、「大規模一部滅失」の場合でも取り壊しや売却が可能になったことで、被災後の復旧がスムーズに進むようになりました。
実際に東日本大震災や熊本地震では、この改正によって多くの被災マンションが迅速に対応できた実績があります。今後も、大規模災害が発生した際には、被災マンション法の適用が重要な役割を果たすことが予想されます。
被災マンションに住んでいる方や、今後の対応を考えている方は、この法律の改正内容を理解し、どのような選択肢があるのかを把握しておくことが大切です。
被災マンション法の適用を受ける際の注意点

被災マンション法を適用して再建や売却を進める際には、通常の手続きとは異なる特別なルールが適用されます。そのため、スムーズな意思決定を行うためには、集会の招集方法や所在不明者の対応、再建・売却後の権利関係、そして期限内の手続きの重要性を理解しておくことが必要です。
ここでは、被災マンション法の適用を受ける際の具體的(ぐたいてき)な注意点について解説します。
集会招集と通知方法
被災マンション法の適用を受けるためには、区分所有者または敷地共有者による集会を開き、決議を行う必要があります。しかし、災害直後は連絡が取りづらい状況が続くことが多いため、通常の集会と比べて特別な招集・通知方法が認められています。
集会招集の流れ
- 招集権者の決定
- 既存の管理者がいれば、その者が招集する。
- 管理者が不在の場合は、区分所有者または敷地共有者の5分の1以上の議決権を持つ者が招集できる。
- 通知の方法
- 通常のケースでは、集会の日の2か月前までに、全員に通知を送る必要がある。
- ただし、災害時は郵便や電話が機能しない可能性があるため、マンションの敷地内の見やすい場所への掲示が認められる。
- 掲示を行った場合、別途できる限りの方法で連絡を試みることが求められる。
- 集会の開催
- 指定された日時に集会を開き、再建や売却についての決議を行う。
- 5分の4以上の賛成を得ることで、再建や売却が決定する。
通知を適切に行わないと、決議が無効となる可能性もあるため、事前に手順をしっかり確認しておくことが重要です。
所在不明者への対応
被災後は、連絡が取れない区分所有者や敷地共有者が出る可能性があります。その場合、意思決定が進まなくなるリスクがあるため、被災マンション法では所在不明者に対する特別な対応が認められています。
所在不明者への対応方法
- 合理的な所在調査
- まず、自治體(じちたい)の避難者リストや連絡先を調査し、所在確認を試みる。
- 家族や親族を通じて連絡を取る努力をする。
- 敷地内への掲示による通知
- 連絡がつかない場合、マンションの敷地内の見やすい場所に通知を掲示することで、正式な通知とみなされる。
- 掲示から一定期間が経過した後、所在不明者も含めた全員の議決権の5分の4以上の賛成が得られれば、決議が成立する。
- 所在不明者の権利について
- 所在不明のまま決議が進んだ場合、再建や売却が決まっても、所在不明者には一定の保護措置が取られる。
- 例えば、売却が決定した場合、その代金は裁判所に供託され、後日所有者が現れた場合に受け取れる仕組みになっている。
このように、所在不明者がいても手続きを進められるようになっていますが、不測のトラブルを防ぐためにも、可能な限り事前に連絡を取る努力をすることが望ましいです。
再建・売却後の権利関係
被災マンション法によって再建や売却が決まると、これまでの権利関係が変わることになります。特に、再建後のマンションの所有権や、売却後の資産分配については、事前にしっかり理解しておくことが大切です。
再建後の権利関係
- 再建決議に賛成した人は、新しいマンションの区分所有者となる。
- 再建に反対し、参加しないことを選んだ人は、持分を時価で売却することができる。
- 所有区画の変更がある場合は、再建決議の際に誰がどの部分を所有するのかを決める必要がある。
売却後の権利関係
- 売却決議に賛成した人は、売却による代金を所有持分に応じて受け取る。
- 売却に反対したが、決議が成立した人も、強制的に所有権を手放すことになるが、その代わりに時価での代金を受け取ることができる。
- 所在不明者の持分は、供託され、後日請求すれば受け取ることが可能。
権利関係を理解しておかないと、後になって「思っていたのと違う」とトラブルになる可能性があるため、事前にしっかり確認しておくことが重要です。
期限内の手続きと決議の重要性
被災マンション法の適用には、決議の期限が設定されています。この期限を過ぎると、特例を利用できなくなり、通常の区分所有法のルールに戻ってしまうため、期限内に手続きを完了させることが非常に重要です。
決議の期限
- 全部滅失の場合 → 政令指定後3年以内に決議が必要
- 大規模一部滅失の場合 → 政令指定後1年以内に決議が必要
この期限内に決議を行わなければ、5分の4の賛成での意思決定ができなくなり、通常の区分所有法に基づく全員の合意が必要になります。つまり、一人でも反対すると再建や売却が進められなくなってしまう可能性があるのです。
期限内に手続きを進めるためのポイント
- 早めに管理組合や所有者で話し合いを開始する
- 専門家(弁護士・不動産コンサルタント)に相談する
- 決議のスケジュールをしっかり立てる
- 所在不明者への対応を早めに進める
災害後は状況が落ち着くまで時間がかかることも多いため、迅速に対応することが求められます。

被災マンション法を適用する際は、適切な手続きを踏まないと決議が無効になる可能性があります。特に、集会の招集と通知方法、所在不明者への対応、再建・売却後の権利関係、期限内の手続きが重要なポイントです。
この法律をうまく活用すれば、スムーズにマンションの再生や売却が進められます。いざというときに困らないよう、事前に基本的なルールを理解し、備えておくことが大切です。
以下の記事では、日常生活で役立つ必須アイテムや、防災に備えておきたいおすすめグッズを詳しくご紹介しています。
以下の記事では、被災者生活再建支援制度の支援対象や申請手続き、受け取れる支援金について詳しく説明しています。
まとめ|被災マンション法を理解し、安心できる未来へ
被災マンション法は、大規模な災害でマンションが深刻な被害を受けた際に、住民がスムーズに再建や売却を進められるようにするための大切な法律です。特に、通常は全員の合意が必要な決定も、5分の4以上の賛成で進められることから、迅速な対応が可能になります。
マンションが「全部滅失」または「大規模一部滅失」した場合、再建するのか、売却するのか、取り壊すのか、それぞれの選択にはメリットと課題があります。法律の適用条件や手続きの流れを事前に知っておくことで、いざというときにも冷静に判断し、より良い未来へと進む準備ができます。
被災したとき、人々は大きな不安を抱えます。ですが、この法律を正しく活用することで、より早く次の生活へ向かう道を見つけることができます。今後のリスクに備え、知識を持っておくことが何よりの安心につながります。
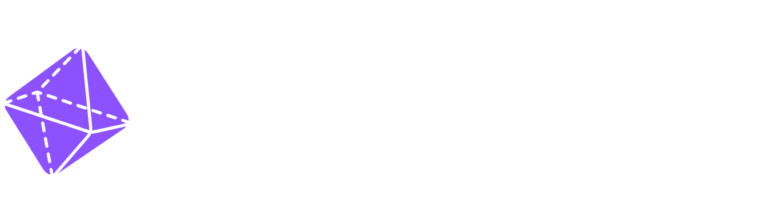


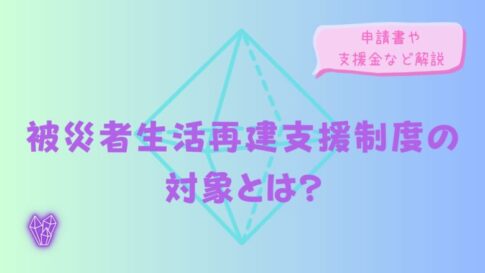
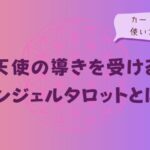
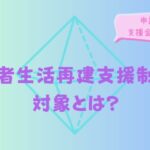
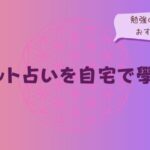
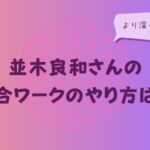

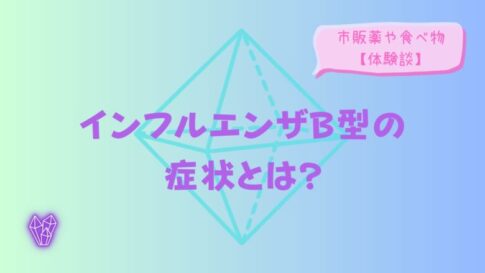
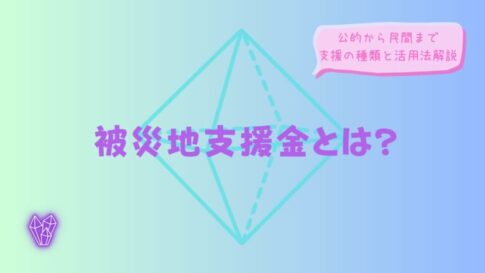

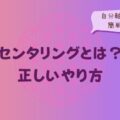
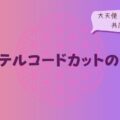
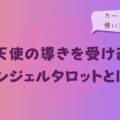
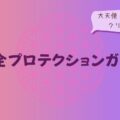
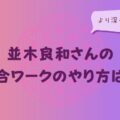
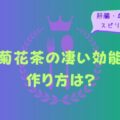
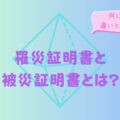
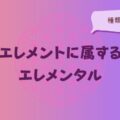
マンションが全部滅失した場合、再建するか敷地を売却するかの選択が求められます。被災マンション法を活用することで、従来の区分所有法では困難だった意思決定をスムーズに進めることが可能になります。
再建を選択すれば住み慣れた場所に戻ることができますが、建築費用の負担が発生します。一方、敷地を売却すれば、新たな生活資金を得ることができますが、売却価格によっては期待した利益を得られない場合もあります。
どちらの選択肢にもメリットとデメリットがあるため、状況に応じて最適な方法を選ぶことが重要です。次の章では、大規模一部滅失の場合の手続きについて詳しく解説します。