災害が発生したとき、被災地の復興を支える「被災地支援金」は欠かせません。
公的支援から民間による寄付まで、さまざまな形で提供される支援金は、被災者の生活再建やインフラ復旧に活用されます。
本記事では、支援金と義援金の違いや、被災地支援金の種類や活用方など、詳しく解説します。
もくじ
被災地支援金とは?

被災地支援金とは、自然災害などの被害を受けた地域や被災者を支援するために提供される資金のことです。
政府や自治体の公的支援、企業や団体、個人の寄付などさまざまな形で集められ、被災地の復興や被災者の生活再建に役立てられます。
一方で、「義援金」とは、被災者個人に直接届けられる寄付金です。赤十字社や自治体が募り、厳正な審査を経て、被災者一人ひとりに公平に分配されます。
被災地支援金と義援金の主な違い
| 項目 | 被災地支援金 | 義援金 |
|---|---|---|
| 用途 | 被災地の復興・インフラ整備・生活支援など | 被災者個人への直接支給 |
| 管理者 | 自治体・NPO・支援団体など | 赤十字社・自治体など |
| 支給対象 | 被災地全体・復興活動を行う団体 | 被災者一人ひとり |
| 使い道の決定 | 支援団体が活用方法を決定 | 被災者自身が使い道を決定 |
被災地支援金を寄付したい場合
どちらも被災者を支援する重要な手段ですが、
- すぐに被災者に現金を届けたいなら「義援金」
- 復興活動や生活支援に役立ててほしいなら「被災地支援金」
と目的に応じて選ぶのがおすすめです。
被災地のニーズに合わせた支援を行うことで、より効果的な復興支援につながります。
被災地支援金の種類

被災地支援金にはさまざまな種類があり、提供元や活用方法によって異なります。
公的機関が主導する制度から、民間団体や企業、さらにはクラウドファンディングや国際的な寄付まで、多様な支援が存在します。
それぞれの特徴を理解することで、適切な支援の形を選ぶことができます。※リンクをクリックすると、記事内にある詳細に移動します
公的機関による支援金
国や自治体が提供する支援金は、被災者の生活再建やインフラ復旧に活用されます。
JASSO(日本学生支援機構)では、災害により生活が困難になった学生を対象に「JASSO災害支援金」を提供しています。
「被災者生活再建支援制度」は、住宅の全壊や長期避難を余儀なくされた世帯に対して、最大300万円の支援金が支給されます。
また、「住宅の応急修理制度」では、半壊した住宅の修繕費用が一定額補助されるなど、公的機関は主に生活基盤の安定を支援する役割を担います。
住宅金融支援機構が提供する「災害復興住宅融資」は、災害により住宅が損壊・滅失した世帯を対象に、低金利で住宅再建や補修のための融資を提供する制度です。
民間団体・企業の支援金
NPOや財団法人、企業が実施する支援金制度もあります。
また、企業によるCSR(企業の社会的責任)活動として、社員による募金活動や企業からの直接寄付が行われるケースもあります。
企業が提供する支援金は、被災者の雇用支援や教育支援などにも活用されることが多いのが特徴です。
クラウドファンディング型支援金
近年では、インターネットを活用したクラウドファンディングを通じた支援も増えています。
「READYFOR」や「CAMPFIRE」などのプラットフォームを利用し、被災地支援プロジェクトを立ち上げることで、個人や企業から寄付を募ることが可能です。
クラウドファンディングは、特定の目的に対して直接支援金を届けられる点が特徴で、復興支援だけでなく、被災地の子どもたちの学費支援や地域コミュニティの再建などにも活用されています。
国際的な支援金
日本国内の支援だけでなく、海外からの支援金も重要な役割を果たします。
国際機関や海外NPO、各国政府が提供する災害支援金は、被災地の医療支援や食料供給、長期的な復興計画に充てられることが多いです。
例えば、国連の「中央緊急対応基金(CERF)」は、被災国に迅速に資金を提供する仕組みを持ち、過去には日本の震災復興にも活用されました。
被災地支援金を受け取るためには、罹災証明書や被災証明書が必要になる場合があります。
これらの証明書は、被災の状況を公的に証明するための重要な書類であり、支援制度の申請時に求められることが多いです。
以下の記事では、罹災証明書と被災証明書の違いや用途、取得のメリットについて詳しく解説しています。ぜひチェックしてみてください。
JASSO災害支援金とは|学生向け支援制度

JASSO(日本学生支援機構)は、災害によって生活が困難になった学生に対し、学業を継続できるように「JASSO災害支援金」を支給しています。
この支援金は、返済不要の給付型で、被災した学生が一日でも早く元の生活を取り戻し、学び続けられるようにすることを目的としています。
JASSOへの寄付をもとに運営されており、公的支援とは異なる形で学生をサポートしています。
申請資格と対象者
JASSO災害支援金を申請できるのは、以下の条件を満たす学生です。
- 対象の学校に在学していること
- 日本国内の大学・短期大学・大学院・高等専門学校・専修学校専門課程に在籍していること
- 海外大学の日本校に在学している日本人学生も対象
- ただし、科目等履修生・研究生・聴講生は対象外
- 自然災害や火災による被害を受けたこと
- 学生本人またはその父母等が住んでいる家が半壊以上の被害を受けた場合
- 床上浸水や自治体からの避難勧告が1か月以上継続した場合
- 入学前・休学中に発生した災害は対象外
- 学業継続の意思があること
- 学校長が「学修意欲があり、修業年限内で学業を修了できる見込みがある」と認めた学生
- 成績不振による留年者は対象外(ただし、留学等による再履修者は申請可能)
支給額と申請方法
JASSO災害支援金は、1人10万円が支給され、返済の義務はありません。
申請方法
- 日本国内の大学等に在籍している学生
在学している学校を通じてJASSOに申請を行います。申請希望者は、申請書および必要書類を学校に提出する必要があります。 - 海外大学の日本校に在学している日本人学生
直接JASSOに申請します。申請要項を確認し、必要書類をそろえて郵送で提出します。提出時は、個人情報保護と発送確認のため、簡易書留などの記録が残る方法を利用することが推奨されています。 - 必要書類の例
- 申請書(JASSOの公式サイトからダウンロード)
- 罹災証明書(コピー可、発行手続き中の場合は申請書類のコピー)
- 学校長の推薦書(申請資格の確認のため)
申請期限と注意点
JASSO災害支援金の申請期限は、災害発生の翌月から6か月以内となっています。
例:令和6年1月1日に発生した災害の場合
→ 申請期限は令和6年7月31日(消印有効)
重要な注意点
- 令和7年3月卒業予定の学生は、学校からJASSOへの推薦期限が令和7年3月31日(必着)となるため、早めの手続きが必要です。
- 罹災証明書が間に合わない場合は、申請手続きのコピーを提出し、証明書が発行され次第、追加で提出可能。
- 申請期限を過ぎた場合は、やむを得ない事情があれば学校を通じてJASSOへ相談できるため、まずは学校の担当窓口に確認することが重要です。
JASSO災害支援金は、被災した学生が学業を継続するための大きな支えとなります。申請資格や期限を確認し、早めの対応を心がけましょう。
被災者生活再建支援制度とは|住宅再建を支援する

被災者生活再建支援制度は、災害によって住宅が全壊するなど、生活基盤に甚大な被害を受けた世帯を支援するための公的制度です。
この制度では、住宅の被害状況や再建方法に応じて「支援金」が支給され、被災者の生活再建を後押しします。
支援金は返済不要であり、被災者の経済的負担を軽減する重要な制度となっています。
基礎支援金と加算支援金の違い
被災者生活再建支援制度では、「基礎支援金」と「加算支援金」の2種類の支援金が提供されます。それぞれの目的と支給額は以下の通りです。
| 支援金の種類 | 目的 | 支給額(世帯) | 単身世帯(3/4) |
|---|---|---|---|
| 基礎支援金 | 被災による生活基盤の損失を補う | 100万円(全壊) / 50万円(大規模半壊) | 75万円 / 37.5万円 |
| 加算支援金 | 住宅の再建方法に応じた支援 | 200万円(建築・購入) / 100万円(補修) / 50万円(賃借) | 150万円 / 75万円 / 37.5万円 |
基礎支援金について
基礎支援金は、住宅が「全壊」または「大規模半壊」した世帯に支給されます。具体的には以下のケースが対象となります。
- 住宅が全壊した世帯
- 住宅の半壊や敷地被害により解体せざるを得なかった世帯(解体世帯)
- 噴火などにより長期間居住できない状態になった世帯(長期避難世帯)
加算支援金について
加算支援金は、住宅の再建方法に応じて追加で支給される支援金です。以下の3つの方法に応じた金額が設定されています。
- 新たに住宅を建築・購入する場合:200万円
- 被害を受けた住宅を補修する場合:100万円
- 公営住宅以外の民間賃貸住宅を借りる場合:50万円
申請条件と支給額の詳細
申請の対象となる条件や支給額の内訳、申請方法について詳しくご紹介します。
申請条件
被災者生活再建支援制度を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 災害により住宅が「全壊」または「大規模半壊」し、生活基盤の再建が困難であること
- 被災時に日本国内の対象自治体に居住していたこと
- 支給対象世帯であること(単身世帯も申請可能)
また、地方自治体によって独自の支援制度が設けられる場合もあるため、各自治体の発表を確認することが重要です。
支給額の詳細と受け取り方法
支援金は、被災者が指定した口座に振り込まれます。申請は居住地の自治体を通じて行い、必要書類の提出後、審査を経て支給が決定されます。
- 申請に必要な書類の例
- 罹災証明書(自治体が発行)
- 被災状況を証明する書類(写真など)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
- 住宅再建計画書(加算支援金を申請する場合)
注意点と申請期限
- 申請期限は災害発生から一定期間内に設定されており、自治体ごとに異なるため注意が必要です。
- 一度申請すると同じ災害での追加申請は不可。支援金の使途を慎重に検討することが重要です。
- 住宅被害の程度を確認し、必要に応じて自治体の相談窓口を利用することを推奨します。
被災者生活再建支援制度は、住宅の再建を経済的にサポートし、被災者が安心して生活を立て直せるよう設計されています。申請条件や支給額を理解し、必要な支援を受けられるようにしましょう。
以下の記事では、被災者生活再建支援制度の詳細について解説しています。
住宅の応急修理(災害救助法)とは|被災者の生活再建を支援

住宅の応急修理制度は、災害で半壊した住宅を持つ世帯が、自力で修理する資力がない場合に利用できる公的支援です。この制度では、市町村が指定した業者を通じて、住宅の最低限の修理を実施し、被災者が日常生活を再開できる環境を整えます。
支援の内容と対象者
住宅の応急修理制度では、日常生活に最低限必要な部分の修理が対象となります。
- 修理対象部分:居室、台所、トイレなど、生活に不可欠な設備
- 支援の上限額:1世帯あたり 57.4万円(平成29年度基準)
- 対象者:
- 災害により住宅が半壊または半焼した世帯
- 応急仮設住宅に入居していない世帯
- 自力で修理する資力がない世帯(※大規模半壊以上の世帯については資力要件なし)
申請方法と注意点
申請は、市町村の窓口を通じて行われます。審査を経て承認されると、自治体が業者に修理を委託し、工事が実施されます。修理費用は自治体が業者に直接支払うため、被災者が費用を負担する必要はありません。
この制度を活用することで、被災後の生活環境の早期回復が可能となります。対象となる場合は、できるだけ早く市町村の窓口に相談し、必要な手続きを進めましょう。
災害復興住宅融資(住宅金融支援機構)とは|低金利で住宅再建を支援する公的融資
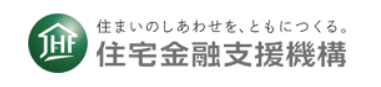
災害復興住宅融資は、被災した住宅の復旧や再建を支援するために、低金利で融資を受けられる制度です。
住宅金融支援機構が提供し、自己資金だけでは住宅の再建が難しい世帯の負担を軽減します。
被災後の生活再建を迅速に進めるため、住宅の建設・補修、ローン借り換えなどに活用できます。
融資の概要と条件
災害復興住宅融資の主な概要は以下の通りです。
- 対象:災害で損壊・滅失した住宅の再建・補修を希望する世帯
- 融資限度額(基本融資額):最大 1,650万円(建設・購入の場合)
- 用途:
- 住宅の建設・購入
- 住宅の補修・増改築
- 被災前の住宅ローンの借り換え
申請方法と注意点
災害復興住宅融資は、住宅金融支援機構の窓口を通じて申請します。
返済期間や金利は、災害の規模や個人の経済状況に応じて調整されるため、詳細な条件は事前に確認することが重要です。
この制度を活用することで、住宅再建のための資金を低金利で確保でき、被災者の経済的負担を軽減できます。
住宅の再建や補修を検討している方は、住宅金融支援機構の公式情報を確認し、早めに相談することをおすすめします。

被災後の生活再建を支援するために、公的制度を活用することで、早期の復興が可能になります。必要に応じて自治体や関係機関に相談し、適切な支援を受けましょう。
被災地支援金を寄付する方法と注意点

被災地を支援するために寄付を考えている方も多いでしょう。
しかし、支援金の使われ方や寄付先の信頼性を確認しないと、意図しない形で利用される可能性もあります。
ここでは、適切な寄付の方法や注意点を解説し、長期的な支援の大切さについても考えていきます。
信頼できる寄付先の選び方
被災地への支援金を寄付する際には、信頼できる団体を選ぶことが重要です。
寄付金が適切に活用されるかどうかは、寄付先の透明性や実績によって大きく変わります。
以下のポイントを参考に、慎重に選びましょう。
- 寄付金の使途が明確な団体を選ぶ
- 支援金がどのように使われるのか公表しているか
- 活動報告を定期的に公開しているか
- 募金詐欺に注意する
- SNSや個人による募金活動は慎重に判断する
- 銀行口座が個人名義の場合は特に警戒する
- 公式サイトのURLが正しいものか確認する
寄付をする前に、団体の公式サイトをチェックし、実際にどのような支援が行われているかを確認することが大切です。
長期的な支援の重要性
災害直後は多くの寄付が集まる一方で、時間が経つにつれて支援の手が届きにくくなる傾向があります。
しかし、被災地の復興には数年単位の時間がかかるため、長期的な支援が不可欠です。
長期的支援が求められる理由
- 被災直後の支援(緊急対応)
- 食料・水・医療品の提供
- 避難所の設置と運営
- 復旧段階の支援
- インフラ復旧や住宅再建
- 生活基盤の安定化
- 復興・再生段階の支援
- 地域経済の活性化
- 教育支援やコミュニティの再生
寄付のタイミングを分散させる、毎月一定額を継続的に支援する「マンスリー寄付」を活用するなど、長期的な視点で支援を考えることが重要です。
企業や個人ができる支援
被災地支援は、寄付だけでなく、さまざまな形で行うことができます。
企業や個人ができる支援を紹介します。
企業による支援
- マッチング寄付の実施(従業員の寄付額に応じて企業も同額を寄付)
- 従業員のボランティア活動支援(被災地での活動を有給扱いにする制度など)
- 自社製品やサービスの提供(飲料・食料・衣類・物流支援など)
個人ができる支援
- クラウドファンディングを活用した支援(READYFOR、CAMPFIREなど)
- ボランティア活動への参加(清掃・物資の仕分け・避難所運営サポートなど)
- 被災地の特産品を購入して経済支援(ふるさと納税や復興支援商品の購入)
このように、支援金の寄付だけでなく、さまざまな方法で被災地をサポートすることができます。
自分にできる形で、持続的な支援を行うことが大切です。
まとめ
被災地支援金は、公的機関から民間の寄付までさまざまな形で提供され、被災者の生活再建や復興を支えています。
支援金には義援金との違いがあり、用途に応じて適切な形で活用されます。
災害の影響は長く続くため、一時的な寄付だけでなく、継続的な支援も大切です。公的な制度を活用することで、被災者の負担を軽減し、必要な支援を受けることができます。
また、信頼できる団体を選んで寄付を行うことで、支援の効果を最大限に高めることができます。
支援の形は寄付だけではありません。ボランティア活動や復興支援商品を購入することも、大切な支援のひとつです。
被災地の人々が一日でも早く安心して暮らせるように、それぞれができることから始めてみましょう。支援の輪が広がることで、被災地の未来を明るくする力になります。
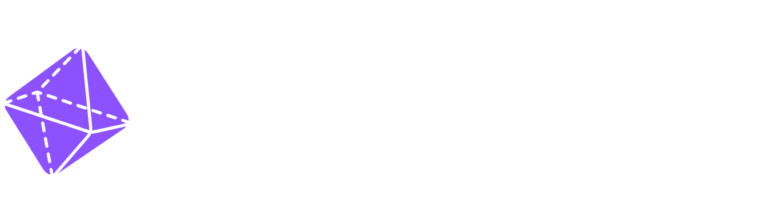

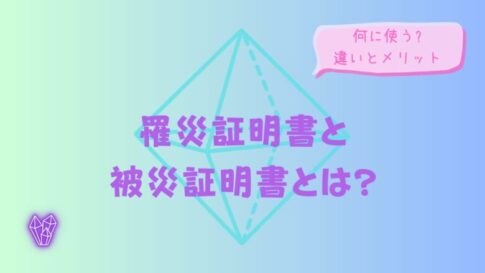
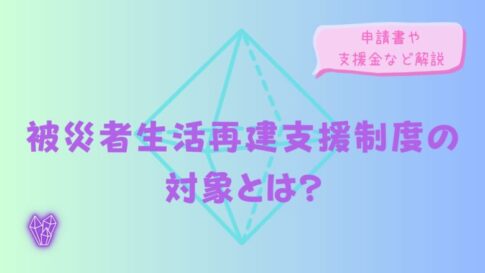
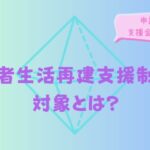


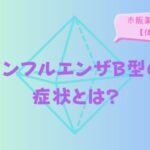
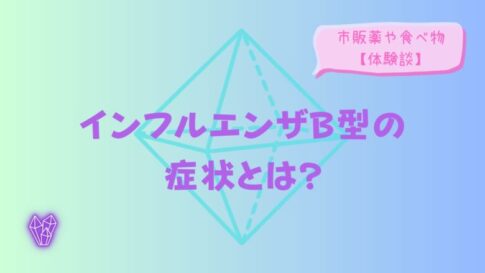
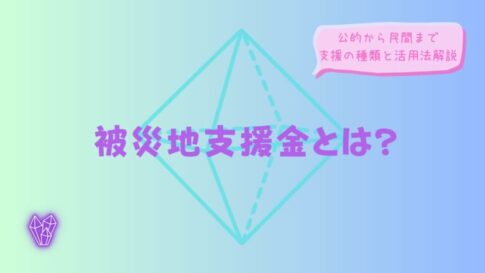

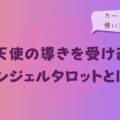
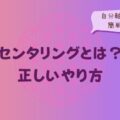
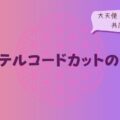
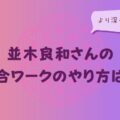
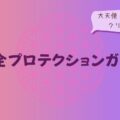
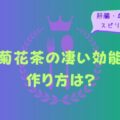
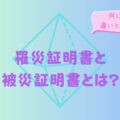
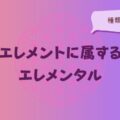
被災地支援金には多くの種類があり、それぞれの特性に応じた活用が行われています。支援を検討する際には、どのような目的で資金が使われるのかを理解した上で、適切な支援方法を選ぶことが大切です。