11月18日の並木良和さんのラジオ番組では、社会に新たな温もりをもたらすフレンドホームにスポットを当てていました。
家庭の温かさを必要とする子どもたちに、安心と愛情を提供するこの制度は、多くの人々に感動を与えています。
子どもたちの未来を共に育む、そんな社会への小さな一歩。この記事では、フレンドホームについて詳しく紐解きます。
フレンドホームとは

フレンドホームは、子どもたちの主體性(しゅたいせい)や可能性を引き出し、自信を育てることを目指している取り組みです。
東京都の乳児院や児童養護施施設にいる子供を、夏休み、冬休み、土曜日、日曜日、祝日など、學校がお休みの時に、受け入れ側の都合の良い日数預かるのがフレンドホームです。
児童養護施設とは異なり、小規模でアットホームな環境を提供し、子どもたちが自分らしさを保ちつつ、社会とのつながりを深めることができる場となっています。
フレンドホームでは、一緒に過ごす家族のような存在となることで、孤立感を和らげ、安心感をもたらします。
さらに、子どもたちの自己肯定感を高め、未来へ希望を持つ力を育むことを目的としています。
並木良和さんが興味がある人は是非氣負わずに問い合わせしてほしいですね、と仰っていました。
フレンドホームへの参加を検討している方々が「何か問題が生じたらどうするか」「受け入れることが大きな責任につながるのではないか」といった不安を抱えないようにと意見に亜矢子さんも賛同しています。
両氏とも、参加を考える方々に心配せず、氣軽に問い合わせてみる事を推奨なさっていました。
問い合わせしてみて無理だと思えば、それでも行動していただくだけで充分良いし、「1日だけのご縁(お役目)もあるんですよ」とも仰っていました。
フレンドホームの役割と特徴

フレンドホームの役割と特徴は、子どもたちが自分自身を認識し、自尊心を築き上げることをサポートすることです。
そのために受け入れ側では、家庭環境や學校環境で得られなかった経験を提供し、子どもの成長を促す活動を行っています。
対話を通じてコミュニケーションを學び、共同作業を通じて協調性を培うこと。そして一人ひとりの意見や感情を尊重し、互いに尊重し合うこと。これらがフレンドホームの活動における基本的要素とされています。
また、フレンドホームは、子どもたちが社会と関わり、社会の一員として自己実現する機会を提供することにも注力しています。

受け入れのスケジュールについて、亜矢子さんは今まで苦労したことは無い、とお話しされていました。
都合で受け入れできない日は勿論断る事が可能で、子どもの部活などの都合で来れない日もあったりもし、そこは無理なく取り組んでいける、との事でした。
フレンドホーム活動の詳細

フレンドホームでは、様々な活動を通して、子どもたちの社会的な成長を向上させます。
活動内容は受け入れ側が考えた事で大丈夫です。お話をきいてあげたり、お出かけするなど。2,300円/日の謝礼が都から出るので、食事代などでマイナスが出る事は無いかと思います。
並木良和さんが仰っていましたが、活動する心持ちについて、「先生をお招きする」と思えば良い、と仰っていました。
どういう事かというと、子どもから學ぶことが沢山出てくるからだそうです。貴重な経験を通して、自分の魂レベルが上がっていくのです。
フレンドホームが提供する安心と心地良さ

フレンドホームで提供される安心感と心地良さは、子どもたちが自分らしさを大切にし、自身の感情や意見を尊重されることから生まれます。

亜矢子さんが最初に受け入れた女の子は、声を大きく出す事が難しく、蚊の鳴くような声でお話していたそうです。
それがだんだんと信頼関係を築いて行く中で、挨拶の声が大きくなり、それが何より嬉しかった事を話されていました。
それぞれの子どもが個別に支援を受けられ、自己の能力と可能性を見つけ出すことができます。
また、フレンドホームでの生活は、日常のルーティンを通じて、自己管理スキルを磨き、社会的なルールを學ぶことができるのです。
このような環境は、子どもたちが自信を持って社会と関わる力を育み、自分らしさを尊重しつつも、他者と協調しながら生きる力を養います。
血の繋がりのない家族という存在の重要性

家族とは、血縁が無くとも存在する皆がそうであるというのがスピリチュアル的理論です。
誠実なコミュニケーションや支援は、自身の能力を最大限に発揮することを可能にし、自己確立に繋がります。
そのため、家族のような存在は個々の成長だけでなく、安心した環境の提供者としての役割も果たします。
暖かい家庭環境の重要性

暖かい家庭環境の提供は、子どもの健全な成長にとって非常に重要です。それは、安心感や自己肯定感を育てる基盤となります。
子どもへ注がれる適切な愛情や注意は、子どもの心の安定に繋がり、自己を認め他人を尊重する価値観を育てます。
また、暖かい家庭環境は、子どもの學習意欲を引き出す助けとなります。未来への期待感や自己効力感を高め、自信を育てていくのです。
さらに、家庭は社会であり、良好な家庭環境は子どもが社会へとスムーズに適応していくための基礎を形成します。
社会貢献とボランティア活動

わたしたちは日々忙しい生活を送っていますが、社会の一員として自分たちにできる社会貢献について考える時間も必要です。
社会貢献とは、和多志(わたし)たち一人一人が自分ができること、自分の持っている力を社会のために使うことです。
ボランティア活動もその一つで、自分の時間や知識を使って人々や社会を助ける行為といえるでしょう。
一見面倒に感じるかもしれませんが、自分が社会に貢献することは自分自身の成長にもつながりますし、何よりも人としての満足感や生きがいを与えてくれます。
ここで注意したいのが、「コップの水(生命エネルギー)が枯渇した状態で他者に何か貢献したいと思う事は危険である」という事です。
もしなにかボランティア活動を行いたいと思った時には、コップの水があふれた状態で行うと問題は無くなります。
もしコップの水の量に自信が無いと感じるなら、迷わずまずご自身を満たす、幸せにする事に行動を移してください。

実際にフレンドホームに取り組むのが難しい場合でも、出来る事は沢山あります。
お友達にフレンドホームの事を話す、でも良いですし、何かしらご自身で無理なく出来る表現を実行して戴きたいと思います。
フレンドホーム活動への参加・問い合わせ先

フレンドホーム活動は、子どもたちが安心して育つことができる環境を提供する社会貢献活動です。
この活動は、一人でも多くの方が参加することで、子どもたちへの愛情や理解を深め、子どもたちが他者に対して愛情を示すことができる強いコミュニティを形成します。
しかし、フレンドホーム活動に参加するためには、何が必要なのでしょうか。また、活動を通じて自身はどのように成長できるのでしょうか。
氣になった方は是非、詳しくはこちらのHPをご覧になってみてください。
まとめ
並木良和さんがホストを務めるラジオ番組「虫の知らせ」で、フレンドホーム里親制度の重要性について議論されました。このセグメントでは、社会的なサポートシステムとしての里親制度の重要性と、それが個人と社会にもたらす利益に焦点を当てました。並木さんとゲストの亜矢子さんは、里親になることに関する一般的な不安や懸念を取り除くことの重要性を強調し、興味を持つリスナーに対し、氣軽に問い合わせてみることを勧めました。番組では、フレンドホーム里親制度がいかに自分の魂の成長に繋がるのかと、社会全體(ぜんたい)の福祉に貢献するかについて、説明しています。
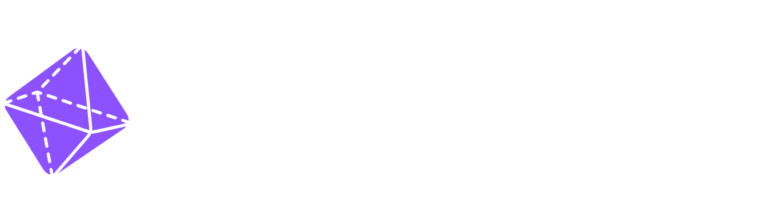

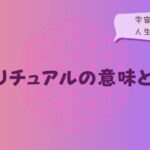
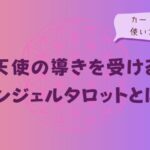
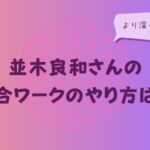
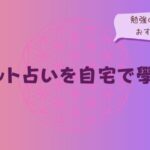
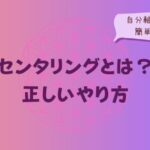
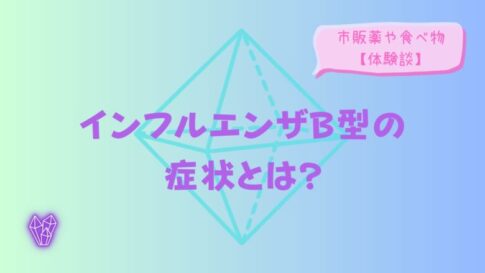
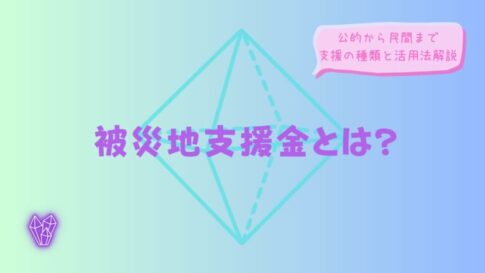

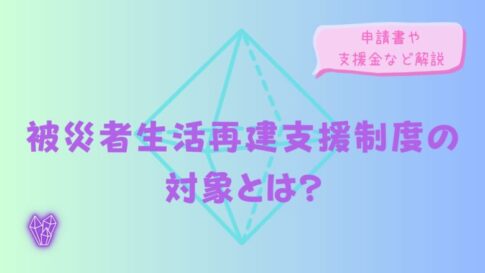
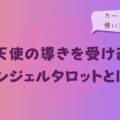
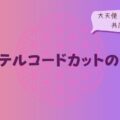
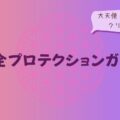
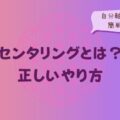
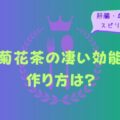
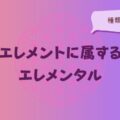

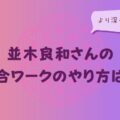
俳優の佐藤浩市さんと亜矢子さんご夫妻はフレンドホームに5年間取り組んでいらっしゃいます。
今回の「虫の知らせ」では、亜矢子さんがゲスト出演なさり詳しくお話しされていました。